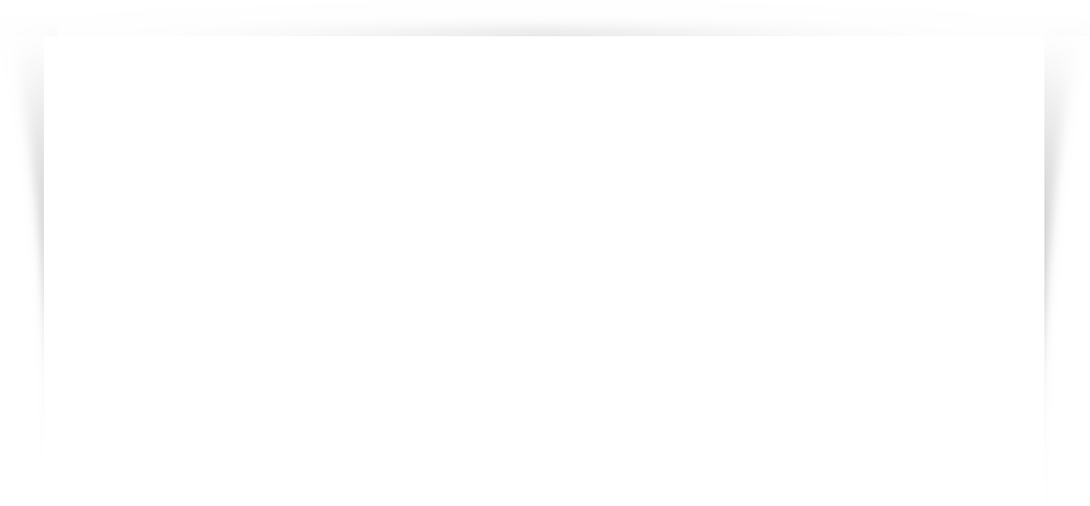
ï¼æå®æ§å¼â¤ï¼ è« æ å 容 ã® è¦ ç´
論文内容の要約 (所定様式⑤) 順天堂大学 論文題目 博士(スポーツ健康科学) 氏名 東明 有美 日本における女子サッカーの言説分析 (Discourse analysis of women’s football in Japan.) (論文内容の要約)(1000 字~1500 字) 【目的】 本研究の目的は、男性優位で発展してきた日本のサッカー界に女性が選手として参入する過程 において、日本サッカーの統括組織である公益財団法人日本サッカー協会(JFA)が女子サッカー に関する言説をどのように構築してきたかを明らかにすることである。 【方法】 本研究は文献考証による理論構築を試みた。 対象文献・資料は、JFAの機関誌内の女子サッカーに関する記事と写真1,465とした。JFAの機関 誌を研究対象とした理由は、JFAの考え方や理念を発信するPR機能を持ち、公式な言説を構築する メディアとして位置づけられるためである。 調査対象期間は、日本で女子サッカーが発生したのが戦後であることから、戦後「Soccer」が 再発行された1948年から2012年までとした。 分析方法は、NZ の女子サッカーに関する分析を行った Cox(2010、2011)の手法(図 1)を踏 襲し、キーワードとキーファクターを踏まえ、内容分析を用いると共に、テキストの背後に潜む 条件を検討し、言説分析を行った。 1.記事を繰り返し読み、言説の中に見られるいくつかの要素を抽出。 2.何が語られ、何が語られていないのかを検討。 言説の作り手や話をした場所や所属機関を踏まえ、立ち位置を確認。 3.一定して確認される類似の意味や声明、または反意語をグループ化。 4.社会慣習、主観や客観がどのように女子サッカー選手に関する文脈の中で述べられているかを 図 1.Cox(2010、2011)の分析手順 【主な結果】 プロダクトライフサイクル理論に基づき女子サッカーの形成(参入)過程を 4 期に分類した。機 関誌における女子サッカーの主な言説は以下のとおりである。 (1)男子サッカー普及のための「客体」として捉えることから出発し、プレーする「主体」へ と変化した。 (2)性差は常に肯定され、女性は「守られるべきもの」「弱いもの」から「平等に扱われるも の」へと変化した。 (3)語りの「主体」は男性であり、女性は語りの「主体」ではない。 (4)女子サッカーを好意的に捉える記事が大半であり、否定的な論調は見られなかった。 (5)国際サッカー連盟(FIFA)に追随し、慎重に策を展開してきたが、2000年以降、重点施策 としての地位を獲得した。 【考察】 機関誌における女子サッカーの言説は、プレーする「主体」として男性性のアピールが許容さ れ、男女平等を掲げる方向に変容してきた。他方で女性を語られる「客体」として位置づけ、 「性 差」 、 「二流感」 、 「異性愛主義」を強調する姿勢を決して崩すことなく構築されてきた。表面的に 女性を受容し、男女平等を肯定しているが、 「二流感・女らしさ=劣位」の基調を内包させ、読者 に性差の浸透を図ってきたと考えられ、日本のサッカー界においては、男性優位のジェンダー関 係が正当化/再生産されてきたと言える。 一方で、2000 年以降、女子サッカーが重点施策として地位を獲得した背景には実力ある男性役 職者の存在が大きな役割をはたしていた。これは、Cox(2010)がニュージーランドで指摘した ことと同じである。それは、女子サッカーが協会の従来のやり方に従順さを見せたことを背景と するもので、単純なジェンダーの主張によるものではなかった。 【結論】 日本において女子サッカーの言説は、第1期から第3期までは外圧に合わせる形で緩慢かつ慎重 に構築された。第4期では、有力な男性役職者の介入によって重点施策として地位を獲得しながら 言説が構築された。しかしJFAは、女子サッカーの立場を変化させながらも、「性差」「二流感」 を基調とし、常に男子サッカーの優位性を確立するための「他者」として女子サッカーの言説を 構築する手法をとり続けてきたと言える。(1295文字、図を除く)
© Copyright 2026