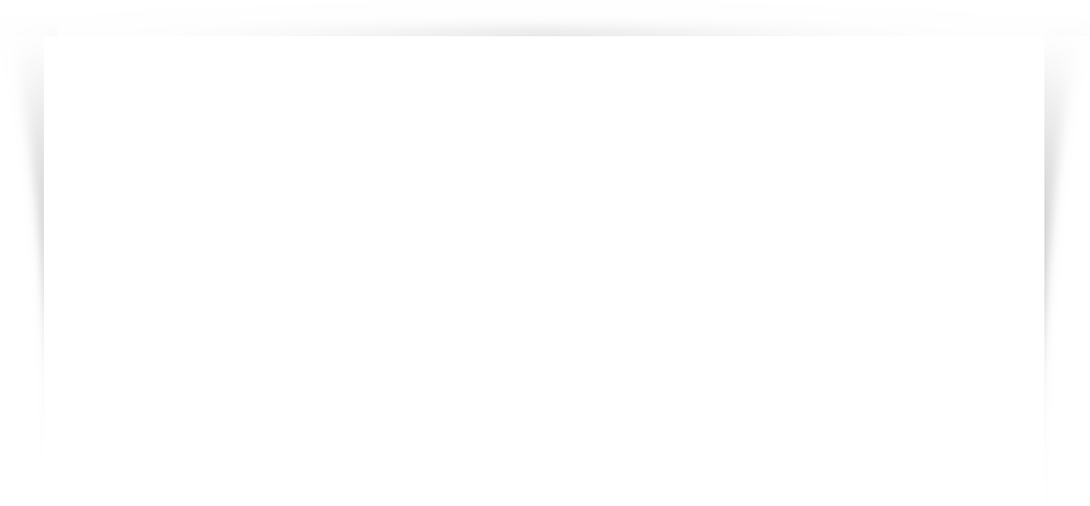
è¦ã/éã
( 篠 村 正 雄 中嶋甚五 左衛門・黒部 勘右衛門が、 詮議に来 邸し番人から 口書を取って 弘前藩江戸藩邸における死者とその扱い(下) )事 故死 いる。 同一八日、老 中戸田山城守 より、御 聞役戸沢弥五 兵衛が呼び出 さ れ、 直接次のよう な申渡しが あった。酒 酔いを番所に 留め置かな かった ここで は、藩邸の内 外で起こった 事故死が どのような扱 いをうけたか 、 また 、弘前藩江戸 藩邸はどの ような関与 をしたかを、 具体例をあ げて考 〕 「江戸日 記」貞享元年 三月一九 日条 覚 一、生国 三河前嶋村 桑江弥 太右衛門 切手遠間 六太夫 深沢次郎兵衛 切 手高木六兵衛 一、死罪之者、親兄弟国所宗旨書付出可申由、指図 ニ付書付遣之、 〔史料 追放となっ た。この取り 扱いをつぎ の史料から みていく。 こ とは不届であ り、二人は 死罪、四人 は江戸一〇里 四方・弘前 藩領から ]延宝 六年(一六七 八)三月一 五日、浜手 屋敷で山野勘 十郎によ 察 していく。 [ ) る様斬り が行われた。 これは山田浅 右衛門に 依頼し、山野 が派遣されて ( きたも のとみられる 。料理一汁六 菜・香物 ・菓子・濃茶 で接待し、様 場 にも 酒・さかなを 用意している 。藩主の 刀剣二一腰が 様されている 。死 体 の入手は、死 罪が行われ た伝馬町の 牢屋から運ば れたもので あろう。 えて届け ている。様斬 り料として、 山野に銀 子二枚、弟子 に銭一貫文が 一、歳 三十三 一、宗旨浄土 宗駒込十方 寺旦那 一 、子供無御座 候 贈られ ている。同五 月一六日にも 様斬りが あり、死体は 正當院に埋葬 し ) ]貞享元年 三月八日、弘 前藩上屋 敷の辻番所に 酒に酔い抜 刀した 一、 女房有之 様斬りのあと 、死体は御 徒目付和嶋 彦兵衛が正 當院に、一分 に書状を添 4 てい る。正當院は 、正洞院の書 き違いと みられる。 [ ( 者が、時を尋 ねにきた。 番人達が棒 で抑えると、 詫び言をい うのでその まま通し た。ところが 、次の松平修 理亮の番 所で押し留め 、幕府目付へ 届け出 たことから問 題が大きくな った。翌 九日、一〇日 、幕府御徒目 付 - 41 - 2 1 2 一、 子壱人男子二 歳 一、女 房有之 一、両親 有之 一、歳十七 一 、生国津軽妙 堂崎村 と 、弘前藩江戸 藩邸内で死 罪を執行し ていることが わかる。 記録 は残されてい ない。幕府の 処刑場で なく、幕府徒 歩目付の検使 のも 動をと ったものとみ られる。江戸 の十方寺 ・国元の海蔵 寺にこのこと の ことが出 来ないが、酒 酔いに対し番 人六人が 関わり、死罪 に相当する行 目付が付添 い、戸塚村で 四人を追放 している。 被害者の側の 様子を知る の で、請人へ渡 したとする 誤りでない かと考えられ る。弘前藩 邸の御徒 ]貞享二 年八月二四 日、往来の 者が、弘前藩 邸西長屋の 水道に倒 ) 広 瀬八郎兵衛 主・五人組・ 死亡した大 工の倅から 手形を取り、 死体を引き 渡すよう指 衛 が、幕府目付 大沢左兵衛へ 出向き、 取次永井安兵 衛から、今晩 中に名 ) ] 元禄二年一〇 月八日、弘前 藩御聞役 河合作右衛門 の小者糸助が 中のため、幕 府目付青木新 五兵衛へ 取扱いを伺わ せたが、登 城中であっ た 。加藤遠江守 の方より幕府 目付と河 合方へ連絡が あった。藩主 が遠慮 ( 使い に出て、加藤 遠江守の柳原 の辻番所 に駆込み、脇 差を抜いて自 害し [ 示されてい る。 戸沢弥五兵衛 持物 から出入の三 河町の大工棟 梁市右衛 門であった。 御聞役戸沢弥 五兵 連絡が あった。番人 が引上げて医 者に見せ たが、すでに 死亡していた 。 ( れ人を発 見、松平下総 守の辻番所へ 、そこか ら弘前藩上屋 敷の辻番所へ [ 一 、姉壱人 一、妹弐人 ニ 一、宗旨 禅津軽 而 海蔵寺 旦那 以上 三月 十九日 愛久沢治左 衛門殿 略) 近藤次 右衛門殿 (中 一 、右死罪次兵 衛死骸、松田 五郎左衛 門方より手紙 添、下谷正洞 院 ヘ遣之、 深 沢次郎兵衛の 死骸は正洞院 、桑江弥 太右衛門の死 骸は請人とな ってい 人が 、弘前藩江戸 藩邸内の馬場 に畳・毛 氈を敷いて検 使を勤めてい る。 これに よると、御徒 目付愛久沢治 左衛門・ 近藤次右衛門 と御小人目付 四 ここでも、藩 主が処分中の ため、慎 重な取り扱い をされている ことがわ 人 に渡したもの とみられる。 このこと は、藩主へも 報告がなされ ている。 とは 勝手次第であ るとされた。 死体は河 合が受取り、 江戸抱えのた め請 ことに なった。幕府 御徒目付より 、乱心者 のため死体を 請人方に渡す こ た。非番の 角南主馬方 で口上書を受 取り、角南 方より青木 方へ連絡する る。しかし、 受取人は逆で あって、 桑江は御国者 で国元の檀那 寺海蔵寺 かる。 ニ 一、右弥太 右衛門死骸 、請人孫左 衛門 相 渡之、 (曹洞宗) と同じ宗旨 の正洞院へ、 深沢は三河 の出で屋敷 奉公している - 42 - 3 4 [ ]宝永三年 (一七〇六 )一一月二 三日五ツ過、 御徒目付桜 庭伝助 ニ 江 御寺 而 御取置可被下 候、右両 人之内清野九 兵衛死骸御寺 遣 申 候、右之儀 ニ付以後如何様之六ヶ敷義御座候共、拙者共罷出埒 大久保五郎兵 衛印 ニ ニ 右之通證文 遣し、今晩 右両寺 て 取置申候 、尤右取置 付 支度金 ) 津軽 越中守内 マ (マ 単 年 戌 十一 月廿五日 が、御金奉 行・御手廻清 野九兵衛を 長屋の二階 で討果たし、 自ら脇差で ) 丙 延命寺 宝永三 江 茂 明、御寺 少 御 苦労懸 ヶ中間敷候 、為其證文如 何 ( 保五郎 兵衛が、まだ 息のある桜庭 から話を 聞いている。 〕 「江 戸日記」宝永 三年一一 月二三日条 ) ニ 〔史 料 マ (マ 与 ニ 一、 私儀 、 清野 九兵 衛日頃 腰ぬ け よ く申 候 付 、堪 忍罷成 不申候 ニ 桜 庭伝介口書 江 付、今晩 九兵衛宿 参 討留申 候、依之私 儀も自害仕候 、此外何 茂 而 意 趣無 御座候由申候 而追付相 果申候、 證文 之事 ( 中略) この 内容を二点に まとめる。 ① 日頃から腰ぬ けといわれ、 堪忍でき ず討果たした 。 法性寺 ここには、 打果たした 理由が述べら れてある 。桜庭は外科 医の診断を受 この 内容を三点に まとめる。 ニ 一人 壱 両壱 歩宛申付候、 間吉 右衛門・小者 久助・御金奉 行定府御 国小人小三郎 、桜庭の付人 甚助、 単」 とあるのは、 本所中之 郷村の天台宗 の寺院であり 、日記 られる。延 命寺は関東 大震災で過去 帳、法性寺 (日蓮宗) は関東大震災 方が禅宗と誤 り、禅宗の示 編を省略 して単と記録 したものでな いかとみ 「 延命寺 金は 江戸藩邸が出 費し、同役に よって埋 葬されたこと がわかる。こ こに、 大久保 は清野と同役 であるが、佐 藤の役職 は御手廻組と みられる。片 付 ③一人に付 き埋葬料一 両一分を納め る。 ②寺へ迷惑を かけないとい う証文を 入れる。 ① 勤番江戸に菩 提寺が無いた め、埋葬 を願い出る。 く。 〔史料 江 寺 遣 之、 證 文之事 ) 一、津軽越中 守家来清野九 兵衛、桜 庭伝介と申者 、一昨晩意趣 有之、 マ (マ 一、清野九兵衛、桜庭伝助死骸、今晩取置候 ニ付、左之通証文仕、 〕 「江戸日記 」宝永三年 一一月二四 日条 そ の他の関係者 から口書を取 っている 。翌二四日の 埋葬の手続を みてい けたが 死亡した。御 徒目付・足軽 目付が、 清野の若党平 沢曾右衛門・ 中 法花 ②その他の理 由は無い。 佐 藤軍大夫印 腹を突き 通す事件が起 こった。これ を聞いて 駆け付けた清 野の同役大久 5 ニ ニ 両人 共 討 果 申 候、 尤両 人共 在 所 者 而 爰元 ニ旦那寺無御座候、 - 43 - 5 6 ・ 第二次世界大 戦で過去帳 ・古文書を 失っており、 このときの 記録が残 っていない 。国元の天台 宗薬王院・ 報恩寺にも この時の記録 は無い。と ) 櫻底傅助事 ころが、 国元の本行寺 (日蓮宗)の 過去帳に 次のようにあ るところから 、 ( 速成 院道覺 〕 「本 行寺過去帳」 桜庭の 菩提寺は本行 寺とみられる 。 〔史 料 廿 三日 宝永三 十 戌 一月 底は庭と 同じ音であり 、死亡年月日 も一致す るので同一人 物とみる。こ ) のこと は一二月一四 日に国元に伝 えられ、 両人の倅は遠 慮の処分を受 け ( 江 一 、右御仕置之 者 申 渡、左之通 、 申渡之覚 御国小人 石渡村与七 江 ニ 蒙儀、 去十月九日之 夜川井藤 太御長屋 盗 入 、品 々盗取質物 御徒目付 差 置 候段 、相 聞 得懸 詮議 候 処、 弥 盗取 候旨 及 白状 言語 道断 ニ ニ 之者 付 、被行死罪者 也、 未ノ三月四日 申渡 足軽目 付 江戸組足 軽 縄 取小人弐人 太刀 取 菩 提寺で追善供 養が執り行わ れ、過去 帳に記録が残 されたものと 考える。 江戸警固二人 てい る。桜庭の方 は菩提寺と同 じ宗旨の 寺へ埋葬され 、国元におい ても 江戸藩邸が寺 院との交渉 から埋葬の 費用まで、負 担している ことがわか 提燈持小人 二人 ニ ニ 右書付 御用人大石庄 司ノ宅 而 、御 目付出席之上 、右御用 而 罷 る。また、 桜庭の方は 江戸で菩提寺 と同じ宗 旨の寺院に頼 み込んでいる ことは明らかである。弘前藩邸では延命寺に寛保三年(一七四三 )、米 覚 一 、御仕置之者 通筋書付左之 通、 江 出候 御徒目付、足 軽目付 相 渡之、 ) 一〇 俵を与えてい るが、どのよ うな理由 で合力米を出 しているのか わか ( ]弘前藩 御国小人石渡 村与七が 、安永三年一 〇月九日の 夜、川井 ら ない。 [ ) 道筋柳嶋御 屋敷暮六時 過罷出、業 平橋より梅若 土手通り、 千 ( 藤太の長屋 で脇差・衣 類を盗んだ。 会所小遣加 勢二人の質 物通帳を借り 、 〕 「江戸日記 」安永四年 三月四日条 りて処刑し ていること になる。与七 の死体は小 塚原の仕置 場に残され、 これは屋敷内 のことなので 、自分仕 置として、弘 前藩は幕府の 刑場を借 ニ ニ 江 右 書半切 認 申渡、書付相 渡候節、 一所 御 目付 相 渡、 三月 四日 江 住より 御仕置場 参 り候 様、 〔史料 果、小塚原で 死罪になった 。 屋 に置かれ、後 に柳島屋敷へ 移された 。同四年三月 四日、取り調 べの結 を添 えたところ、 質入れができ た。この ことが発覚し 、与七は掃除 方長 山田屋 に質入れしよ うとしたが断 られた。 次に会所小遣 又右衛門の手 紙 6 - 44 - 7 8 片 付けられたも のとみられ る。手紙を 書いた又右衛 門は叱の処 分を受け ①御附御小 姓とみられる 甚太郎が、 酒酔いのと ころを深手を 負わされ、 こ の内容を三点 にまとめる 。 ) の跡式を 認めないとあ る。甚太郎は ここに示 された例にあ たるので、跡 ( これに関して は、寛文一 二年(一六 七二)の規定 に、乱心・ 喧嘩・自害 ③ 忌中届の差し 戻しを願い 出るように させる。 扱っ てきた。 ②倅よ り忌中届が出 ているが、変 死のため 、内済の含み を持たせて取 り 江戸藩邸 内で死亡した 。 ている。 ) 白川藩で は、自分仕置 として鈴が 森の刑場で 処刑している 例があると ( ころみ ると、処刑場 を借りること ができた のであろう。 また、会津藩 で は、 正式な手続き を経て郷中間 の死体を 海に投棄して いるので、こ のよ う な処理も可能 であったも のとみられ る。 ]文化六 年九月一八 日、弘前藩 邸御広敷御中 居・御半下 女中三人 の衣類が 紛失し、屋敷 に出入れの町 方同心に 詮議を依頼し た。一一月一 式は認 められないこ とになる。そ こで、弘 前藩邸の方は 内済に済ませ て [ 七日に なって江戸町 奉行が掃除小 人多次郎 ・善次郎を調 べ、そこから 国 跡式 を認めたいと している。こ の方針に そって跡式は 認められ、親 類縁 ) 下り をした与吉に 疑いがかかり 、呼び寄 せることにな った。国元で は屋 者 により菩提寺 へ埋葬された ものとみ られる。この ような跡式を 願い出 ( 敷 内の事件とみ ていたが、江 戸町奉行 所扱いとなっ ているので、 与吉を る際は、寺請 証文を添え ることにな っていた。 ( ) ]赤石 愛太郎の母 の仇討は、 安政元年六 月一九日、水 戸城下にお いて行 われた。同年 五月、仇討を 国元で願 い出たが、許 可されず出奔 し [ 江戸へ登らせ る処置をと った。与吉 は江戸町奉行 で白状し死 罪となった 。 ] 天保一一年四 月一〇日、伴 甚太郎の 不審死があっ た。 自分仕置き でなく、幕 府の手で小塚 原か鈴が 森で処刑され たとみられる 。 [ 〕 「江戸日記」 安政元年閏七 月一四日 条 高杉友衛支 配 ニ 様 之義 者 御規 定も 有之 義 付 、 断状 差戻 候 之旨 申出 候、 依之右 ニ ニ 申者 被 致殺害候 付 、無程仇討 願差出、国 元出立所々探 索いたし候 当三 ヶ年以前子年 中母義、武州 児玉郡八 幡山町出生吉 之進事元吉と 津軽越中守 殿留守居 始末早速可申出筈之処に、今無其儀甚等閑之致方 ニ候、尤次男 ニ 処、 去月 十 九日 七ツ 時頃 、 当城 下向 井町々 お いて 、右元 吉見当 り 赤石愛 太郎 同道之由も相 聞得候間、長 之助詮議 之上、早速可 被申出旨、御 ニ ニ 討果候得共 、国法も有 候義 付 、如 何様 仕 置被申付 候様いたし 度候 当寅二 十一歳 てい る。水戸藩に 提出した本人 の口上書 に次のように 理由が述べら れて あ る。 〕 「江 戸日記」天保 一一年四 月一〇日条 一 、伴甚太郎義 、去ル三日之 夜、法恩 寺東通り裏門 辺、酒酔之者 之 〔史料 〔史 料 ニ ニ 所為 も 可有之哉、 深手負候 付 其場所より 召連、於宿先 相果候 由、無相違 相聞候、然 処倅長之助 義、親甚太郎 病死之旨忌 中及 9 江 附御小姓組 之頭 直 より申遣 之、 - 45 - 7 8 ニ ニ 断候得 共、変死之義 内済之含 而 断状 差出候義 も 可有 候哉、右 10 9 江 ニ 間 、委細口上書 を以右町役 人 申 立 付 、尚更其筋役 人共相尋候 処、 書面之通聊 相違之筋無之 候間申立之 候、 江 江 ニ 一 、同五日、山 鹿友蔵 相 渡候様、 御目付 相 渡候申渡書、 左 、 赤石愛太郎 其方儀、 今度母之仇を 打留候段、 水戸様衆よ り被申越、公 辺 ニ 御伺済 付 、為 請取 役 之被 差 遣候 条難 有 奉存 、猶 又此 上 共万 七月 母の仇 元吉を討果た したので、ど のような 仕置にも服す るといってい る。 事謹 慎候様可被致 候、 これでは、七 月五日に申 渡書を目付 山鹿へ渡した ことになっ ているが、 七月 水戸 藩では、江戸 城御城付久世 十太夫か ら老中松平和 泉守の意向を 伺っ 〕 「江戸日記」 安政元年七 月十五日条 た 。幕府の意向 は、水戸藩 から弘前藩 に次のように 伝えられた 。 〔史料 ニ 元 吉と 申 者討 果候 付 、愛 太 郎引 渡 方等 得御指 図被 申度、 先達而 水戸殿 城下於向井町 、津軽越 中守家来赤石 愛太郎と申者 、母之仇 弘 前藩として謹 慎を命ずると いうもの である。国元 での出奔が処 分の内 五日 の誤りとみら れる。仇討に ついては 、幕府への伺 いも済ませた ので、 二日に 延期してほし いとの申入れ があった 。よって、申 渡書の日付は 一 一七日に 受取りに出立 をしようとし ていたと ころ、水戸藩 から二一か二 及御達候之処、右元吉義吉之進事元吉 ニ相違無之哉否之義、聢と 容とみられる 。これが、 弘前藩の愛 太郎に対する 処分である 。二六日に 右、御進 達写 、引渡候様御 附札を以御 指 水戸をたち 、二七日に 牛久宿と荒川 宿間にお いて、駕籠の 中で脇差で喉 ハヽ ニ 図 付 、 尚 又越 中守 家 来方 を突い た。介抱しな がら夜通し運 び、二八 日に江戸屋敷 の長屋に着い た 不致候間、今 一応得と相 糺無相違候 武州八幡山村出生之由、香具渡世 ニ而、四五年已然より津軽領荒 とこ ろで死亡して いる。御徒目 付の検分 のあと、碩運 寺に埋葬され たこ 相達 相糺候 処、 前書吉 之進事 元吉義 江 ニ 川村 と申処 参 り 落着居者 而 、愛太郎母致 殺害、其場 より立去候 と が、次の史料 からわかる。 江茂 ニ ハ 江 ニ 者 無 相違相聞候間 、愛太郎事 越 中守家来 引 渡被申 而 、可有御 〔史料 一、右別紙 左 ) 江 郎 御尋 之 上、 愛太 郎 親類 之 者 可 仰 含 候様 奉存 候、 尤 大小 其 右愛太郎法号 今日立駒井 弥太郎持参 仕候、委細之 儀者右弥太 江 雲寺 葬 送相済申候、 右葬式之 儀等悉皆御物 入を以被仰付 候、 マ (マ ニ 茂 儀相 果候 付 、 御徒目付検 使 相 済 、二十九日夜 本所石原町碩 一筆致 啓上候、去月 晦日立御飛 脚之節得貴 意候、赤石愛 太郎 ニ 〕 「国日記」安 政元年八月五 日条 座候、此段尚 更及御達候様 被申付候 、 七月 水戸藩 が、もう一度 元吉に間違い がないか 確認し、その 後に弘前藩に 引 き渡 して良いとす るものであっ た。七月 二五日になっ て弘前藩の御 目付 山 鹿友蔵が、水 戸で愛太郎を 受け取っ た。この時の 愛太郎への申 渡が次 〕 「国日記」 安政元年閏 七月一日条 の史料からわ かる。 〔史料 13 - 46 - 11 12 第取揃差下 申候、右様御 含夫々御取 扱可被成候 、此段得貴意 茂 ニ 外 衣類等 有 之、当時大小 之研 取 懸居候間、当 伺之上御序 次 (左脇) 純孝院恵雲玄 燈行道居士 (正面)復 讐孝士赤石愛 太郎墓 ( 右脇)嘉永七 甲寅年七月 二十九日 〕 「恵 林寺墓石」 国元の 恵林寺(曹洞 宗)が菩提寺 で、墓石 には次のよう に刻されてあ る。 〔史 料 安 政元甲寅年七 月廿九日 純孝院恵雲玄 燈行道居士 碩運寺 の墓石は「玄 燈」の二字が 、過去帳 より多い。こ れは、葬式に 付 坂巻 並衛 候、恐惶 謹言 閏七月 六日 御 目付中様 この内容を三 点にまとめ る。 ②戒名 は駒井弥太郎 が国元へ持参 するので 、愛太郎の親 類に知らせる 。 けら れた戒名が、 一か月後に墓 石を建立 する際に追加 して贈られて もの 赤石愛太 郎源行道 ③大 小は研ぎに出 しており、衣 類と共に 後日届ける。 と 考える。恵林 寺の方は、碩 運寺の墓 石建立後に国 元へ戒名が伝 えられ、 ①葬式は 弘前藩の費用 で済ませた。 こ の時、一一代 藩主順承は在 国であっ たが、江戸で 隠居していた 前藩主 愛太郎に子 供が無いた め、親類か ら礼次郎を 養子とし、百 石、表書院 それを基に刻 まれたもの とみられる 。 たものとみ られる。藩 の出費は、葬 式料に一 両二分・三四 〇文、大小の 番で召 抱えている。 礼次郎は、翌 年七月、 弘前藩より碩 運寺での墓参 を 信順は仇討を 賞賛してい るので、愛 太郎に関する ものは藩の 費用で賄っ 砥代が 二両二分、石 碑の建立・開 眼供養に 三両一分、水 戸までの迎え に 許さ れ江戸へ登っ ている。水戸 で世話に なった人に謝 礼したいと申 し出 ) 二四 両一分二朱・ 五五四文、水 戸で世話 になった者に 一〇両となっ てい た が、江戸藩邸 はすでに礼を している のでそれには 及ばないとし ている。 ( ) ]弘化三年(一八四六 )、大川端屋敷の足軽とみられる常七が、 勤番所の衣 類を盗み、 江戸町奉行所 の取り扱い になった。 常七は出羽国 [ と で、内外に弘 前藩の存在を 示してい ることが理解 できよう。 弘前 藩邸は、墓石 に「復讐孝士 」と刻ま せて親の仇討 ちを顕彰する こ 使用し たものかはわ からない。 の脇差、仇 討を報じた 江戸瓦版、母 親の片袖を 所蔵する。 脇差が仇討に 弘前城天守閣 史料館は、愛 太郎の子 孫から寄贈さ れた備前国 住景光銘 ( る。 〕 「碩運寺過 去帳」 津 軽公徒士赤石 愛太郎事廿一 才 嘉永七 寅歳七月 碩運寺の過去 帳には次のよ うに記載 されている。 〔史料 廿九日 純孝 院恵雲行道居 士 〕 「碩運寺墓 石」 碩運寺に現存 する墓石は定 府の書家 平井東堂の筆 になるといわ れる。 〔史料 - 47 - 16 9 14 15 庄 内の無宿者で 、吟味中に 牢死し、衣 類は返されて きた。関係 する本所 松坂町質屋 喜兵衛は五貫 文、同町五 人組持店作 兵衛は三貫文 の過料にな った。 このよ うに事故死の 場合、弘前藩 邸が幕府 ・江戸町奉行 所・他藩との 対応 をせまられ、 問題の処理に 当たらな ければならな いことが明ら かに な った。特に、 藩主が幕府 より処分を 受けている期 間は、自ら 死者の取 り扱いに慎重 を期し、指 示を与えて いる。埋葬の 経費も藩費 よるものも あった。 菩提寺と同じ 宗旨の寺へ埋 葬されて いる三例は、 いずれも藩が 関与し た場合である ことが明らか となった 。 ) 「江戸日記」貞享四年一〇月一〇日、一六日条。 ( )『 憲教類典(六 )』(「内閣文庫所蔵史籍叢刊」第四二巻)、汲古書院、 ( 一九八四。御咎の項によると、幕府からの処分中、大名・旗本の屋敷内 に死体を埋葬し、難儀しているため、夜になってから密かに死体を門外 ( ( ( ( ( )右同日記元禄二年二月一二日条。 )右同日記元禄元年五月一五日条。 )右同日記元禄元年三月六日条。 )右同日記元禄元年一月二日条。 )右同日記貞享四年一一月一八日、二五日条。 に出すことを、認めていることがわかる。 ( )右同日記元禄二年一一月一二日条。 ) 「江戸日記」貞享四年一一月一六日条。 ( )右同日記元禄四年六月二日条。 ( )『新編弘前市史資 料編 画課、二〇〇〇年。 ) 「江戸日記」元禄一四年七月一八日条。 )右同日記寛政五年八月一八日七日条。 ( ( ( ( ( ( ( )右同日記安永四年一二月一八日条。 )右同日記安永三年一一月一六日条。 )右同日記文久三年八月七日条。 )右同日記文化九年一〇月一〇日条。 )右同日記安政六年三月二三日条。 )右同日記安政四年八月一八日条。 )右同日記天保一〇年三月一六日条。 )右同日記文化一一年五月一六日条。 ( )右同日記文化四年二月二七日条。 ( 2 病死 の時の拝借金 は、御目見以 上が一両 、七歳未満が 御定の半減と さ ( 4 ) 史 料 番 号 二〇 二 』 弘 前 市 企 画部 企 5 (近世 6 ( 7 3 れ ていたが、借 財・薬料等の 返済につ いては個々の 事情を考慮し ている ため、御定の 内容を明確 にすること ができなかっ た。上総小 人の場合は 、 2 8 ( - 48 - 3 9 12 11 10 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 弘前藩邸が 二分を支給 し、人宿の負 担として いないことが わかった。 死亡者 の遺品は、藩 の経費で負担 し、国元 の親類縁者に 届けているこ とが 判明した。 事 故死にあって は、いずれも 江戸藩邸 が関与し、菩 提寺と同じ宗 旨の 寺院を探した り、なかには 埋葬の費 用を藩の経費 で賄う場合 もあったこ ) 「新選津軽系譜」弘前市立図書館蔵。 とが考察で きた。 註 ( とは時候の挨拶が行われている。 『 新 訂 寛 政 重 修 家 譜 』 第 八 、 続 群 書 類 従 完 成 会 、 一九 六 五 年 。 久 世家 1 ) ( )はじめにの註( )前掲書。 ( )右同日記安政五年七月一五日条。 ( ( ( ( 江東区深川二丁目。過去帳は天保一三年から昭和一九年(一九四四)ま でを記載している。 ) 「江戸日記」延宝六年三月一五日条。 ) 「江戸日記」貞享二年八月二四日条。 ) 「国日記」宝永三年一二月一四日条。 ) 「上方分限帳」弘前市立図書館蔵。 ) 「江戸日記」安永三年一〇月二六日条。 より愛太郎水戸表 ニおいて母之敵吉之 丞を内留候一件抜書」同館蔵。清 「赤 石愛太郎敵討之一件」弘前市立図書館蔵 。「赤石愛太郎母変死取扱 日、八日条。 )「 江戸日記」安政元年七 月一五日、一九日、三〇日、閏七月二日、五 ) 『御用格寛政本』弘前市教育委員会、一九九一。 ) 「江戸日記」文化六年九月一八日条。 ( )氏家幹人『大江戸死体考』平凡社新書、一九九九。 ( ( ( ( )本行寺、日蓮宗。弘前市新寺町九二。 ( )右同日記宝永三年一一月二三日、二四日条。 ( )右同日記元禄二年一〇月九日条。 ( ( )右同日記貞享元年三月一八日条。 ( ( )恵然寺、臨済宗。明治二年(一八六九)に寒光寺(円覚寺派)と改称。 ・古文書五点は二〇〇四年追加指定を受けた。 ( )高橋家所蔵文書。高橋家住宅は一九七三年国重要文化財指定。蔵二棟 17 一九三二。 )右同日記安政二年八月一日条。 氏家幹人『武士道とエロス』 、講談社現代新書、一九九五。 ( )右同日記弘化三年一二月二四日条。 ( ) 正洞 院・長寿寺・ 碩運寺過 去帳にみえる 死 )正洞院過 去帳にみえる 死 三 ( ( 下 谷 の 正 洞院 と 弘 前藩 と の 関 係に つ いて ふれ る。 正洞 院は 慶長 六 年 (一六〇一 )、秋田藩主佐竹義宣の室を開基とする。室は那須家の出で あり、弘前藩四代藩主津軽信政は、天和二年(一六八二 )、二子資徳を 那須家 の養嗣子に入 れている。 この那須家 と津軽家との 縁戚関係が 、正 洞院 と弘前藩を結 びつけたか どうかは明 らかでない。 弘前藩上屋 敷が元 禄 元年(一六 八八)まで、 神田鷹匠町 にあったの で、下谷の正 洞院とは 比較的近い 距離にあった といえる。 正洞院過 去帳は、次の 二種類ある 。 ①文化 四年(一八〇 七)から嘉永 五年(一 八五二)まで のもので、二 分 冊に なっているが 、弘前藩に 関する記載 はみあたらな い。 ②文政四年(一八二一 )、一二代関重が整備したもので、三分冊になっ ている。 ) 「江戸日記」で確認できるものが一〇人いる。過去帳に無く 、「江戸日 ( 後 者 に 弘 前 藩 に 関 す る も の が 三 一 人 み え る 。 こ の 死 者 三 一 人 の う ち、 蔵)には、由緒書の「伊吹茂草」等が含まれている。 記」 に記載されて いる者が二名 いる。そ れらは、徒士 と江戸足軽 の二名 野 熊 助 が 明 治 四 〇 年 に 編 集 し た 「 津 軽 藩 士 赤 石 愛 太 郎 復 讐 録 」( 同 館 43 42 26 三浦寺水「赤石愛太郎水戸の仇討 」 (『郷土誌むつ第三輯』陸奥郷土会、 - 49 - 1 27 25 24 28 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 ) 手 屋敷で藩主の 腰物の様斬 りが行われ 、死骸は金子 一分に添状 を付し、 ( で あるが、中間 ・人足が過 去帳に記載 されているの に、藩士身 分の徒士 ) 御徒目付が正當院へ埋葬している。この正當院と正洞院は 、『御府内寺 様 斬り・死罪に なったもの は、病死と 違いその後の 追善供養も 期待で われ ている様斬り の死骸も引き 受けてい るものと考え られるからで ある。 正洞院 が死罪になっ た者の埋葬を 認めてい るところから 、それ以前に 行 ( でありなが ら、抜けてい るのがどう してなのか わからない。 次のように 社備考』 に寺院名が見 えない。正當 院は正洞 院の書き間違 えとみられる 。 五 子 月 〕 「正洞 院過去帳」 甲 津軽 之者也 過去帳に 名前の記載の ないものがあ る。 〔史料 朔日 貞 享元 きず、緊急避 難的な取扱 いで、寺側 が過去帳には 載せなかっ たものであ 吟 雲禅定門 これは 、「江戸日記」により、小人で参勤交代のため江戸に登った大光 ) ろう。 ( 弘前藩 邸が責任を持 つという証文 を入れて 、菩提寺のな い武家奉公人 寺村惣左 衛門であるこ とが特定でき る。同じ ように、池田 源兵衛は藩士 でなく塗師であることがわかる 。「江戸日記」は、正洞院の例から、江 元 禄元年になっ て、弘前藩上 屋敷が神 田から本所へ 移ると、正洞 院と や死 罪・様斬りの 死体の埋葬を 依頼して いることが理 解できよう。 戒 名から、居士 ・大姉は三人 で、家老 と上級藩士の 家族である。 信士 の結び付きは 疎遠になっ ていったよ うである。し かし、家老 津軽靭負家 戸藩 邸の死者全員 を記載したも のでない ことが明らか である。 は一人である 。禅門一〇 人の中に表 坊主が二人含 まれるが、 藩士クラス や大湯彦八 家は、檀家 として繋がっ ているも のとみられる 。 )長寿寺過去 帳にみえる死 とみられる 。禅定門一 七人の中で、 苗字を有 する者が五人 、名前だけの ( ) 〕 「 江戸日記」文 化二年八月 二日条 茂 昨年 中 度 々 願 申出 候得 とも 難 被 仰付 、此 度又 々 願申 出、同 院 一、柳島長寿 寺申出候、勘 定奉行附 紙申出候、長 寿寺御扶持方 之儀、 〔 史料 長寿 寺から弘前藩 への申し入れ をみてい く。 までは 合力米四石一 〇人扶持を渡 している 。 弘前藩は、 長寿寺に対 して文化二 年以前から、 安政四年( 一八五七) いく。 ( 弘 前藩柳島の下 屋敷に隣接す る柳島の 長寿寺と、弘 前藩の関係を みて 2 者が一 二人で、郷中 間・人足が三 人含まれ ている。禅定 門は、武家奉 公 人ク ラスに付され た戒名である といえよ う。 葬 送の仕方は、 元禄元年三月 六日、石 田次左衛門の 又者武太夫の 場合、 ) 藩主への報告 後、郷中間四 人に足軽 目付が付添っ て、正洞院 に埋葬して ( いる。郷足 軽は棺桶担 ぎとみられる 。この時、 弘前藩邸は 、正洞院との 約束に より葬送する としているの で、葬送 に関して両者 の間に、なん ら かの 取り決めが存 在していたも のであろ う。 こ の他に、事故 死でふれたよ うに、貞 享元年(一六 八四)三月一 九日、 ) 死罪になった 深沢次郎兵衛 が、藩か らの添状を付 されて埋葬さ れている ( が、過去帳 に記載はな い。また、延 宝六年(一 六七八)三 月一五日、浜 2 - 50 - 1 之 儀者御国元ゟ詰 合之足軽 小人之類、軽 者病死之節者 、其度毎 る。この中 で「江戸日記 」で確認で きる者が三 二人ある。過 去帳コノ部 の は、文化二年 から明治四 一年(一九 〇八)まで、 一三二人の 記載があ ) 介成 ニ者葬送金差遣、一体先年御国凶作之節ゟ津梁院等も御合 無縁に次 のような記載 がある。 助 ( ニ ニ 力御減被 仰付、今以半 減 相 渡居 、勿論、当時 御省略中 付 、御 〔史料 元治 二年 九月二 三日 仝 近藤 古伯 「 位牌アリ」と ○印のあるも のが、廃 藩以前で七例 、以後に一二 例あ あろ う。 るので 、近藤古伯は 医者とみられ 、長寿寺 が小者とする のは聞き誤り で 分から返 納することに なった。拝借 金一両は 百石取りの藩 士が対象であ 「江戸日記」 には同役の 小川泰嘉よ り片付金一両 の拝借願が 出て、給 悟 本祖煎居士 (津軽小者) 〕 「長寿 寺過去帳」 与 扶 持方 増之 儀 、難 被及 御 沙汰 儀 奉 存候 旨、 申 出之 通右之 趣申 江 通候 様、御聞役 申 遣 之、 こ の内容を三点 にまとめる 。 ①長寿寺より 半減になっ ている合力 米回復の願い が出ている 。 ②国元の 凶作により、 菩提寺津梁院 でも半減 の取り扱いを している時な ので、 増やすことは できない。 ③病 死した勤番の 足軽・小人の 埋葬を引 き受けている 。 こ こでは、弘前 藩邸・長寿寺 双方とも 、合力米が勤 番の中間・小 人の埋 戒名から廃 藩以前をみ ていく。居 士一五人で 、内訳は院・ 居士が一〇 る。 天保八年( 一八三七) になって、 墓地が狭隘 のため火葬に しての埋葬 人、居 士が五人いて 、いずれも上 級藩士と 家族とみられ る。信士が二 六 葬を引き受け ていること によるもの であることを 認識してい る。 を申し 出ている。以 後、弘前藩邸 はこの内 談を基に、火 葬は長寿寺、 土 人で 、内訳は院・ 信士が三人、 信士が二 三人である。 禅定門が六一 人、 ) 葬は 碩運寺へ送る 取り扱いをす ることに した。ところ が、安政四年 四月 禅 門・童女が各 一人である。 足軽一人 は禅定門、小 者八人の内、 信士一 ( 二 八日、改めて 勤番で軽輩の 者の埋葬 を引き受ける 申し出があっ た。弘 ・禅定門七人 、小人二二人 の内、信 士三・禅定門 一九人であ る。禅定門 信士三 ・禅定門一人 である。この 信士三人 は苗字があり 、家老の用達 ク ) 前藩としては 、先年より火 葬は長寿 寺、土葬は碩 運寺として きたが支障 が武家奉公 人に対する 戒名であるこ とがわかる 。家老の又 者が四人で、 長寿寺 側としては、 安政江戸地震 で本堂が 潰れており、 加えて、弘前 ラス で、施主にな った家老側の 意向が戒 名に反映して いるものと思 われ ( なかったこ とから、両 寺の選択を親 類縁者に任 せることに している。 藩邸 からの葬送が 激減し、財政 基盤が弱 体したことか ら、この申入 れに る。 童女・孩児 ・嬰女各一 人である。 廃藩以後では 、居士が二一 人、内訳 は院・居士が 二〇人、居士 一人、 な ったものとみ られる。 長寿寺過去帳 は明治期に三 分冊に整 備されている 。アイウエオ 順で、 アの部の初 めに無縁、 次に有縁と配 置されてい る。弘前藩 邸に関するも - 51 - 3 過去帳・墓石・「江戸日記」と一致がする者が四人、過去帳・墓石の 一致が一人、墓石・「江戸日記」の一致が一人である。 廃藩以後 も長寿寺に埋 葬されてい る者が二八 人いる。これ は、明治四 年、知 藩事津軽承昭 が横川端屋敷 に住み、 津軽家の中心 がここになっ て こ の内容を二点 にまとめる 。 ①地震によ り建物が大破 し、再建に あたり檀家 と同じように 藩士へ奉加 を願い出 ている。 ②勤番 で病死した多 くの者を埋葬 している ので、藩から 一両一分六文 を 寿 寺を頼ってい るものと考 えられる。 戒名と位牌を 立てている 例からも、 葬を依頼して いることを 認識してい ることがわか る。弘前藩 から合力米 こ れによると、 弘前藩邸が 碩運寺に対 し、勤番の者 が病死した 場合、埋 出し 、藩士への奉 加は断る。 檀家の契約を 維持し、親 類縁者によ って戒名の上 昇を志向し ているとみ を出して いる記録は残 っていない。 いっ たため、津軽 家に仕えた者 や、弘前 藩に所縁のあ る在京の者が 、長 られる。 過去帳 は二種類ある 。 ①元 禄期からのも ので、弘前藩 に関して は、元文五年 (一七四〇) の追 良 瀬酒之丞の妹 、寛延二年( 一七四九 )の桜井元次 郎の二人だけ であ る。 ②弘化四年 (一八四七 ) 、一九代雲 嶺の手で 整備されたも のである。 後者に は、弘前藩に 関係する文化 八年から 明治七年まで の死者を二一 五 ) - 52 - 長寿寺 が弘前藩邸の 武家奉公人の 埋葬を引 き受け、それ に対して藩邸 )碩運寺 過去帳にみ える死 ) 側も 合力米を与え ていることが 明らかに なった。 ( ( 碩運寺 は江戸安政大 地震で壊滅的 な打撃を 受け、再建に あたり弘前藩 に そのなかで 、 「江戸日記 」嘉永四年 、抜参りの 青森町の三太 郎の場合 、 過ぎないこと が明らかであ る。 人ある。ここでも、「江戸日記」は石運寺の約四〇%を記録しているに 人記 載している。 このなかで「 江戸日記 」から確認で きるものが、 八八 ) 〕 「 江戸日記」安 政四年八月 一三日条 マ (マ ニ 居向皆潰 ニ相成候 付 、此度檀家一統勧化之上再建致度 ニ付、御 ( 掃除方 へ預けられて いたが病死し 、片付金 二分で碩運寺 へ送られた記 載 〕 「 碩運寺過去帳 」 江 江 家中 勧 化御 免被仰付度旨 申出、詰合 病死数多同 寺 葬 送も 有之 〔 史料 三四良事 廿二才 があ る。 銀 壱枚 ハヽ (十五日)嘉 永四 年 亥 十月 鉄開禅定門 津軽中 間 ニ ニ 候 付 、御 時 合柄 御 座候得共、銀弐枚被下置、御家中 江勧化之 儀 者御断之儀、 委細御目付 申出之通被 仰付候様、左 候 四拾目五分積 を以、渡方之 儀共被仰 付候様、惣高 壱両壱分六文 目之旨、附 紙之通申付 之、 5 〔 史料 次の ような申し入 れを行ってい る。 本所石原町 の碩運寺と 弘前藩の関 係をみる。 3 一、御目付申 出候、石原町 碩雲寺去 々卯十月大地 震之節、本 堂并住 4 こ の過去帳の記 載から、こ こに埋葬し ていない娘の 追善供養を 、母親が 葛西處一 事 [ 仲間 ) 春道良 忍信士 津 ( 軽殿 同 三十四 才 施 主西口深弥 津 軽国人 ]嘉永六年三 月廿一日 清 園禅定門 ]安政元年八 月一五日 エ 国元 送 骨 越 後産渋木勇助 事 万助と どのような関 係にあったの かはわか らない。 [ 唯 法伝心禅定門 津軽本治良殿 内對馬中蔵 内弟子 播 磨屋宗七子 分 ]安政五年 三月六日 遺骨 は国元の越後 へ届けている 。 [ 津軽小人 岩五郎は、 上総小人の 雇頭播磨屋宗 七の子分な ので、宗七 が依頼したこ 岩五郎 渋木勇 助は、支藩黒 石藩対馬中蔵 の内弟子 であり、葬式 だけが依頼さ れ、 二八才 万助は、所 属する組頭 から寺に依頼 したもの である。施主 西口深弥が、 中村勘介より 頭来 万助 後日、 誰かが供養し 、その際に贈 られたも のとみられる 。 があり、 寺へ依頼した ものと考えら れる 。 「春道」 は追号になっ ており 、 中田屋多七は 、藩に出入 りする商人 とみられ、中 間伊作と何 らかの関係 伊作事 ]天 保十年三月廿 六日 三 太郎と死亡の 日付が一致 し、この日 に死亡した者 が他にいな いので、 津軽 藩 [ 依頼してい るものである 。 ) 八月 ) 縁 弘前中田 屋多七 「太」と「 四」の一字違 いがあるが 同一人物と みられる。国 元への取扱 いは、調 査の結果によ るとしたが、 どのよう になったか不 明である。 また、 安政四年八月 一八日、勧学 生葛西處 一の死亡の場 合、拝借金は ) 一両 二分であった 。本人の大小 ・衣類・ 書物六〇〇冊 は、本馬二疋 分三 ( 両 二五六文を弘 前藩邸が支 給して国元 へ送り届けて いる。碩運 寺(曹洞 〕 「碩運寺 過去帳」 安 ( 政四年 同 ( 宗)の過去帳 に、次のよ うに記載が あり、ここに 依頼して埋 葬している 。 〔史料 一八日 宏覚 院清方日忠居 士 年 巳 八月一八 日 〕 「法立寺過去 帳」 丁 宏学院 清方日忠居 士 こ れに関して、 国元の法立寺 (日蓮宗 )の過去帳に は、次のよう にある。 〔史料 安政四 江戸勤 学登ニテ葛西 彦一叔父也 これ によって、處 一は菩提寺を 日蓮宗と するものの、 同宗の寺院に は葬 送 されず、江戸 藩邸が碩運寺 に埋葬を 依頼している ことがわかる 。戒名 は「覚」と「 学」の一字の 違いがあ るが、荷物と ともに国元 に知らされ 、 親類の彦一 が法立寺で 追善供養を行 い、過去帳 に記載され たものとみら れる。 ]天保八年 六月一八日 ニ 親 付 置 次に 、過去帳から 依頼者のある 者を五例 取り上げる。 [ 西室智香信 女 津軽殿馬 屋之与一之 姥志 - 53 - 2 3 4 5 6 7 〔付箋〕不葬 1 と がわかる。抱 元側が埋葬 しているが 、 「 江戸日記」に 記載がない ので、 弘前藩邸が 片付金二分を 支給したか どうかは不 明である。 園 林清光信士 安 (政三年 同 〕 「碩運寺 墓石」 ) 津軽 藩徒歩之菊 池八百吉 墓石には次 のように刻さ れてある。 〔史料 (右側 )祠堂金付 過去帳に は弘前藩以外 に、播磨屋 惣七願・播 磨屋宗七子分 ・播磨屋万 五郎子 分の記載があ り、播磨屋と 碩運寺の 関係が濃いも のであったこ と (正 面)安政三季 丙辰八月十日 弘前藩士菊池 八百吉 凉 心院殿園林清 光居士 がわ かる。 こ のように、さ まざまな葬 式・追善供 養のあり方が あったこと が理解 できよう。 □□ 過去帳 は信士号、墓 石は院殿居士 号となっ ている。墓碑 名から、後に 国 (左側) 菊池慎□ 士三人 、その他藩士 五人、勧学生 二人、中 間・小人各一 人である。中 間 元か ら親類縁者が 、追善供養を おこない 、墓石建立・ 祠堂金を納め た時 戒名から 廃藩以前をみ ていく。居 士が一九人 で、内訳は勤 番七人、徒 ・小 人になぜ上級 戒名の居士が 付けられ ているのか疑 問である。信 士は 国元からの追善供養については、寛政四年(一七九二 )、毛内有右衛 に 追号されたも のとみられる 。 人各三人、禅 定門は一六 七人で中間 ・小人・陸尺 等、禅定尼 ・孩女各一 門から親宣 応の河内に ある先祖墓参 願いが出 され、一年間 の暇願いがみ 二 三人で、内訳 は勤番四人、 藩士九人 、家族三人、 坊主一人、中 間・小 人である。 禅定門は武 家奉公人に付 けられた 戒名で、約七 七%を占めて け た師匠に対す る謝礼に、百 日の暇願 いを出して認 められている 。親類 とめら れている。同 年、笠井兼蔵 の親の場 合は認められ ていない。文 化 現存する墓石二基は、過去帳・「江戸日記」の記載と一致する。一つ 縁者による追 善供養は、過 去帳・墓 石から七人、 史料から二 人だけであ いるこ とがわかる。 廃藩以後は四 人の埋葬 よりみられな いことから、 弘 は事故死で述 べた赤石愛太 郎である 。もう一つの 徒小頭格御 先御徒菊池 る。役務を 休み、経費 をかけて遠距 離の墓参に 出かけるこ とは、容易な 一三 年、林兵九郎 は、江戸で病 死した親 兵左衛門の墓 参と、諸伝授 を受 八百吉は 、「江戸日記」から、本人の大小・荷物は、交替下りの山崎寅 ことで はなかったと みられる。隠 居した者 であれば比較 的簡単に暇願 い 前藩 関係者との関 係は無くなっ たものと みられる。 之助に 付けて、弘前 藩邸が軽尻馬 賃三分二 朱と五九〇文 を負担して送 り ) が提 出出来たもの であろう。 ( 碩 運寺は弘前藩 邸の武家奉公 人の埋葬 を、多数引き 受けているに もか かわらず、藩 邸側が長寿寺 と同じよ うに合力米を 与えない理由 を説明す ることがで きない。 - 54 - 9 届け ていることが わかる。 〕 「碩運寺過去 帳」 過 去帳に次のよ うにある。 〔史料 十日 8 ( )長寿寺・ 碩運寺過去 帳と弘前藩 庁日記(江戸 日記)にみ える死 長寿寺・碩運寺過去帳の年号の重なる部分と 、「江戸日記」の死者数 江 年表』がコレ ラとしてい るにもかか わらず、弘前 藩江戸藩邸 はコレラ と認識せず 、流行病とみ ている。弘 前藩邸は、 藩主の菩提寺 浅草常福寺 に、病気 平癒の祈祷を 依頼している 。 同六年 、麻疹に似た 病気が流行し 、弘前藩 邸の蘭学医佐 々木元俊は、 )である。「江戸日記」は、文化一三年から文政 一 〇 年ま で 欠 け、 明 治 四 年の 廃 藩 で終 わっ て いる 。こ の欠 けた 部分 は 国元 から阿片、江 戸でホフマン 液・ラウ タニユムを入 手して治療に あた を比 較 したの が 表( 「国 日記」で補っ た。天保八年 六月六日 、長寿寺から の申し入れで 、弘 っ て い る 。元 俊 は 嘉永 元 年 、江 戸 で 牛痘 法を 学び 、 文久 二年 (一 八六 ) 前 藩邸では火葬 は長寿寺、 土葬は碩運 寺へ埋葬する ように取り 計らった。 二 )、国元で種痘館を創設して種痘の普及に努めている。江戸藩邸で種 ( ところが、安 政四年四月 二八日、再 度の長寿寺か らの申し入 れがあった 痘が何時 から実施され たかは明らか でない。 長寿寺・碩運 寺過去帳は安 ) が、弘前 藩邸は寺院の 選択は親類縁 者に任せ るとした。こ の間、長寿寺 政六年 に合わせて二 〇人を記載し 、この内 足軽・津軽小 者・津軽小人 ・ ( への埋 葬が断絶して いることがわ かる。長 寿寺は寺院の 財政的基盤に な 箱持 が一二人を占 めている 。 「江 戸日記」は 死者二六人 を記載してい る。 たという。弘 前藩邸では 、藩主家の 人までが罹患 する状態に なった。病 文 久二年、麻疹 が猛威を振る い、日本 橋上を一日二 〇〇の葬列が 通っ 天保六年、麻 疹流行の際 、弘前藩邸 は医者山辺玄 節に掃除部 屋の病人 人が多く、 月抱えの上 総小人が引き 上げたた め、掃除小人 が不足する事 の とみられる。 の療治に当 たらせたが 、薬品が不足 し、二〇 人分で二両を 用意している 。 態 に 陥 っ て い る 。 長 寿 寺 ・ 碩 運 寺 過 去 帳 は 合 わ せ て 二 一 人 、「 江 戸 日 わかる。その うち江戸日記 に名前の あるのは九人 のみで、残 り二七人、 邸 から碩運寺に 埋葬されたの が三六人 で、三三人が 中間であった ことが 去帳は廃藩 以前で三一 五人を記載し 、居士が三 四人で約一 〇%、信士が 分を「国日記 」で五〇人補 充すると 、合わせて六 〇〇人にな る。両寺過 表からみて、「江戸日記」は五五〇人を記載し、この日記に欠けた部 ( 上 総 小 人 も 不 足 し 、 月 抱 え で 一 〇 人 の 雇 い 入 れ を し て い る 。『 武 江 年 記」 は三九人を記 載している。 七五%にあ たる者の記 載はない。弘 前藩邸内の 人員は、目 付が根帳によ 四九人 で約一六%、 禅定門が二三 一人で約 七三%、禅門 が一人で約〇 ・ ) って把握しており 、「江戸日記」にみえる死者は、その一部分に過ぎな 病気の治療 法が未熟な 時代にあっ て、麻疹・コ レラの流行 は手の施し いる役割を知 ることが出来 る。 は 、約七割を占 めている。こ のことか らも、弘前藩 邸が両寺に依 頼して 三% 、その他三人 で約〇・九% になる。 武家奉公人に 付けられた禅 定門 戸の町は野辺 送りの列が絶 えず、棺 桶が高騰、寺 院も葬儀で暇 なく、死 安 政江戸地震に ついては、次 章でふれ る。同五年コ レラが流行し 、江 いこ とが明らかで ある。 ( 表』 には天保七年 に麻疹、同八 年に疫癘 流行とある。 この年に、弘 前藩 ) って いる埋葬・追 善供養の絶え ているこ とに困り、申 し入れを行っ たも 3 者二万八千余人、火葬九千八〇〇人という状況であった。しかし 、『武 - 55 - 4 表(3)弘前藩庁日記(江戸日記)と長寿寺・碩運寺過去帳の死者数 年号 西暦 文化2 文化3 文化4 文化5 文化6 文化7 文化8 文化9 文化10 文化11 文化12 文化13 文化14 文政1 文政2 文政3 文政4 文政5 文政6 文政7 文政8 文政9 文政10 文政11 文政12 天保1 天保2 天保3 天保4 天保5 天保6 天保7 天保8 天保9 天保10 天保11 天保12 天保13 天保14 弘化1 弘化2 弘化3 弘化4 嘉永1 嘉永2 嘉永3 嘉永4 嘉永5 嘉永6 安政1 安政2 安政3 安政4 安政5 安政6 万延1 文久1 文久2 文久3 元治1 慶応1 慶応2 慶応3 明治1 明治2 明治3 明治4 明治5~ 計 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 弘前(江戸) 長 寿 寺 弘前(江戸) 碩 運 寺 弘前(江戸) 備 考 死者数 死者数 藩士 又者 家族 その他 有 無 死者数 藩士 又者 家族 その他 有 無 2 3 3 2 1 10 5 3 0 3 1 1 1 1 津軽人、播磨屋惣七願 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 3 5 3 1 5 4 7 2 3 11 0 3 1 8 5 3 10 12 7 麻疹流行 28 2 2 2 36 34 2 9 27 疫癘 18 11 10 1 1 10 22 22 22 4 18 6 2 2 1 1 16 8 8 7 1 23 7 7 6 1 16 6 6 4 2 10 6 6 2 4 17 6 6 3 3 8 7 6 1 3 4 7 5 5 2 3 13 5 4 1 4 1 5 1 1 1 7 7 7 5 2 2 10 10 2 8 2 4 3 1 1 3 1 5 4 1 1 4 津軽国人、施主西口深弥 12 17 16 1 11 6 黒石藩対馬中蔵内弟子 91 6 6 4 2 安政江戸地震 17 10 10 4 6 7 1 1 1 9 9 4 5 14 1 1 1 3 3 1 2 コレラ流行 26 14 14 5 9 6 6 3 3 麻疹に類した病気 1 2 2 2 2 2 2 12 5 5 5 3 3 2 1 39 17 15 2 4 13 4 4 2 2 麻疹流行 13 12 12 5 7 2 1 1 1 1 5 15 14 1 2 13 16 12 12 5 7 9 13 12 1 5 8 2 3 3 3 0 ― 1 1 ― 1 1 ― 3 3 1 1 ― 25 3 22 3 3 600 132 103 3 4 22 32 70 215 201 4 3 7 88 123 長寿寺申入れ 天保8年6月6日、安政4年4月28日 弘前(江戸)は、弘前藩庁日記(江戸日記)であり、欠本の文化13年より文政10年までは、弘前藩庁日記(国日記)で補った。 - 56 - よ うがなかった 。そのなか にあって、 弘前藩邸は、 医者による 投薬、御 二五 - - 二一に移転。 )右同日記安政四年八月一八日条。 二。 ( )長寿寺、臨済宗永源寺派、江東区亀戸三丁目一〇 ( )右同日記安政四年四月八日条。 ) 「江戸日記」天保八年六月六日条。 ( )碩運寺、曹洞宗、本所石原町より明治四三年に荒川区西尾久二 ) 「江戸日記」嘉永四年六月二二日条。 ( )法立寺、日蓮宗、弘前市新寺町七三。 )右同天保六年二月二一日条。 ) 「江戸日記」安政三年八月一一日条。 )平凡社、一九六八。 安政 江戸地震に おける死 安 政江戸地震は 、安政二年( 一八五五 )一〇月二日 、荒川河口を 震源 四 歴史民俗博物館研究報告』第一一六号) 、二〇〇四。 )福井敏隆「幕末期弘前藩における種痘の受容と医学館の創立」 (『国立 ) 「江戸日記」安政六年八月一七日、九月一日条。 ( ( ( ( ( ( ( ( - 目見以下へ の琵琶葉湯の 配布による 病気対策を 講じている。 また、藩主 家の菩提 寺に祈祷を命 じ、その最高 権威を利 用して邸内の 安寧を図って いるこ とが理解でき よう。 この ように、三ケ 寺の過去帳を 通して、 弘前藩邸の死 者の扱いを明 ら か にすることに あった。正 洞院には様 切りと死者の 埋葬を依頼 している が、合力米の 支給はない 。藩士の一 部も菩提寺と していたが 、上屋敷が 本所へ移 ると寺との関 係は疎遠にな っていっ たものと考え る。 長寿寺 に対しては、 勤番の埋葬を 依頼し、 そのことを寺 側、江戸藩邸 の両 者が認識して いることを明 らかにで きた。合力米 はそのための 支給 と みられる。 碩運寺にたい しても、勤 番の埋葬を 依頼している ことは、寺 側と江戸 藩邸の間で 認識してい る。このこと は、安政 江戸地震の際 、寺側が復興 二。 のため に勧進を求め ていることか らわかる が、合力米の 支給がない理 由 がみ つからない。 註 ( )正洞院、曹洞宗、台東区下谷二丁目六 - この名簿は、 足軽・掃除小 人・上総 小人の人数を 記すのみで、 名前を挙 残 っていない。 ところが、同 七日、八 〇人として死 者名を記載し ている。 れ死七 九人、怪我 人二八人と数 え、別帳に 名前を載せ たとあるがこ れは 弘前藩邸 の被害を「 江戸日記」で みていくと 、翌三日に 建物の被害と 潰 ) とし、マグニ チュード六・ 九、震度 六であった。 死者一万人余 、倒壊家 ( )右同日記元禄元年三月六日条。 ( )右同日記貞享元年三月一八日条。 ( )右同日記延宝六年三月一五日条。 ( )名著出版一九八六。 ( 屋一万四三 四六軒で、町 方の被害は 特に深川・ 浅草・本所で 多かった。 ) 「江戸日記」貞享三年四月二日条。元禄四年七月一一日条。 ( )右同日記貞享元年五月一日条。 ( 8 1 - 57 - 9 11 10 19 18 17 16 15 14 13 12 2 3 4 5 6 7 江 ニ 除頭 者 私共 而 可申付候間 、附紙之通 申付之、 ニ 手羽、入瓶 代料十八匁 而 御入目、 げ ていない。上 屋敷一三人 ・浜屋敷一 九人・三ツ目 屋敷四七人 の合計が 七九人であ るのに、八〇 人としてあ るのは、計 算間違いとし てみるより この内 容を二点にま とめる。 与 〆一歩仁 朱 四 百弐 拾七文 用番久 世大和守に即 死男四六人・ 女三三人 、合わせて七 九人と届け出 て ①病 気養生中に病 死したので、 掃除方に より善行院へ 埋葬する。 ほかにな い。国元への 名簿も同じく 八〇人と してある。同 一〇日、幕府 いて 、これが弘前 藩として公式 に認めた 死者数になる 。 入瓶代は火葬 の際の壺で あるとみら れる。このこ とから、近 藤歳徳は地 ② 片付金は地震 での死者の 例に倣い支 給する。 得を新たに追 加し、死者 を八〇人と しているが、 近藤の埋葬 までは言及 震で大怪 我をし、それ がもとで一三 日になっ てから死亡し たものと考え 白石睦弥氏は、「秘日記」から「後死近藤歳得」とある表坊主近藤歳 していな い。また、勤 番の者に○印 が付して あるのが、他 の史料に見ら られる 。 た。 その ほか、鈴木栄 太郎から同一 二月二七 日に次のよう な申し出があ っ れない 点である。こ の日記は、弘 前藩江戸 屋敷の被害状 況を記録して い ) 〕 「江戸日記」 安政二年一 二月二七日 条 ①鈴木栄次郎 から地震で娘 が死亡し ているので、 回向料受け 取りの申し 出がある。 ②目付 人別帳に載っ ていないが、 調べて間 違いがないこ とがわかった の ニ 而 相 果候 面々 、 葬方 の振 合 を以 、掃 除 方手 而 取 片付 被仰付 候 下賜したもの である。これ は、前藩 主より回向料 の下賜がある と聞き、 死 亡の人別帳に 記載がないが 、調査の 結果間違いが ないので、回 向料を で、 回向料一分を 支給する。 善行院 江御頼入之儀并為埋葬料金仁朱、外塔婆料百 ハヽ 様、 左候 一二月にな ってから申 し出たもので あることが わかる。 - 58 - るも ので、筆者名 を知ることが できない が、上屋敷に いた兄から確 実な ( 情 報を得ており 、信頼できる ものとみ ている。 〔史料 ニ 一、 鈴 木栄 次郎 申 出候 、娘 地震 之節 相果候 付 、 回向料 被下方 之儀 この他に災害 を記録して いるものに 「金木屋日記 」がある。 これは、 弘前城下で 質屋・酒屋 を営んだ有力 商人武田 又三郎による もので、日頃 ) ニ 申 出 、最 初御 目 付取 調人 別 無 之 候 得 共 、 無 相 違 相 聞 得 候 間、 ( から家 老大導寺家に 出入りして確 実な情報 を手にしてい る。地震の死 者 〕 「江戸日記 」安政二年 一〇月一三 日条 こ の内容を二点 にまとめる。 為回 向料壱歩被下 置候様、 附紙之通申付 之、 〔史料 後死の表坊主 近藤歳得につ いて、次 の史料をみる 。 の 情報によるも のとみられる 。 につ いては大道寺 家と、江戸の 医者手塚 元端からの情 報は、それぞ れ別 2 江 江 文、同寺 送 方之儀共 、御目付 被 仰付候様 、猶手配向 之儀、掃 いた し候間、取片 付金頂戴被 仰付度旨申 出候得共、頃 日変事ニ 一、坊 主小頭申出候 、表坊主近 藤歳徳儀、 病気之処養生 不相叶病死 1 弘 前藩の公式な 死者七九人 に、近藤歳 得・鈴木栄次 郎の娘を追 加する と、八一人 になる。幕府 への届け出 の七九人が 、通説として 取り扱われ ているの を八一人に改 めたい。 次に、 八一人の死者 がどのように 取り扱わ れたかをみて いくことにす る。 地震の翌々日 の五日に、混 雑のため 、死骸は検死 無しで片付け が可 ) る。 ②一人に付 き、埋葬料二 朱・塔婆料 一〇〇文、 合計六両二歩 二朱と五貫 三〇〇文 になる。 ③他の 寺院に断られ たが、善行院 は早速承 諾してくれた ので、挨拶料 二 〇〇 疋を出す。 こ の時点では、 五三人の埋 葬が予定さ れていた。加 えて、一〇 月二八日 ( 能 になった。と ころが、江 戸の町中が 騒然となって おり、寺院 が倒壊・ に怪我により 自分の手で 檀那寺に埋 葬できない者 を、弘前藩 の手で善行 ) 焼失していて は、菩提寺 を持つもの でも埋葬が容 易に進まな かったよう 院へ仮埋 葬するという 布達が出てい る。 ( ) 同一一 月七日に勘定 奉行から、地 震の騒ぎ で追善回向が できずにおり 、 ( である。 長寿寺・碩運 寺は、弘前藩 邸の武家 奉公人の埋葬 を受け入れて きたが 、本堂が倒壊 し、今回は断 ったもの とみられる。 弘前藩邸は埋 葬 ) 惣回 向を一〇両で 行ったらどう かという 意見が出され た。これに対 し、 ③勤番・季 節抱えの者 は、今後も供 養ができ ないため、永 代祠堂金とし て五両 を寄付する。 4 - 59 - ( を引 き受けてくれ る寺院を探し 、本所法 恩寺塔中善行 院(日蓮宗) に頼 一 二月八日にな って弘前藩邸 は次の四 点を確認して いる。 ) み 込んだ。これ まで、善行院 と藩邸は 結びつきがな かったことが 、次の ①埋葬した四 七人の惣回 向料として 七両を出す。 ( 史料からわか る。 〕 「江戸日記 」安政二年 一〇月七日 条 江 〔史料 ニ 一、勘 定奉行申出候 、此度変事 付 相果 候人数、法恩 寺境内善行院 ④定 府の者は、各 自で檀那寺へ 埋葬して いるので、回 向料一人に付 き百 疋 を出す。 ニ 江 ニ ニ 付 百文積を以、 同寺 被 下置候様、 尤自分 而 御扱 不 相成之分 、 含めた四七 人が善行院 に埋葬された ことがわか る。残り四 人と、鈴木栄 結果からみる と、死者八一 人の内、 定府三〇人は 菩提寺、近 藤歳得を 江 江 同寺 御 仕向之儀 者、御目付 被 仰付候様 、申出之通 被仰付之、 院へ は約五八%が 埋葬されたこ とが明ら かになった。 太郎の 娘の埋葬先は 不明である。 死者のう ち菩提寺へは 約三七%、善 行 ハヽ 次のような方 針を出してい る。 残 された問題は 、死亡した者 の跡式で ある。弘前藩 邸は、同二三 日に この内容を三 点にまとめる 。 〔史料 〕 「江戸日記 」安政二年 一〇月二三 日条 ①自分で埋 葬できるも のを除いて、 五三人を法 恩寺塔頭善 行院に埋葬す 江 御 目付 被 仰付候様、 承伏 いたし候間、 為御挨拶金 二百疋可被 下置候哉、左 候 ニ ニ 但 、点 羽、 急 変之場 合 付 、 外寺 院 而 御断之処、同寺 ニ而早速 ニ 差引残五拾参 人 御 座候間、 六両弐歩二 朱と五貫参百 文御座候 、 江 御頼 入之上、同寺 相 送 候間、為埋 葬料壱人二 朱、塔婆料壱 人 3 申 遣之、 この内容を 三点にまとめ る。 江茂 并に今相不 済倅有之分者 、忌明之処 に而御定之 通申出候様、 倅 ①地震の 死亡者につい ては、安堵跡 式の取り 扱いをする。 但 、諸手足軽 無之二男 三男并孫等有 之分、親類 ゟ申出候様 、子孫無之分 者是 ②組頭 の扱いで親族 より跡式を申 立たせる 。 ニ ニ 一 、今度地震 而 致死去候族、 跡式可被 下置候 付 、御目見相済 候倅 又身寄 之者養子申立 候、可被 仰付哉之儀、 沙汰之通右之 趣夫々 国 元へは個別に 情報が伝え られる場合 もあり、死者 を出した家 では忌中 ③男 子がない場合 は、身寄りの ものによ り願い出るよ うにさせる。 こ の内容を三点 にまとめる 。 に入っていた が、ここに 至って跡式 の申し立てが できるよう になった。 江 申通 候様、御目付 申 遣 之、 ①御目見が済 んでいる倅 は問題がな いが、済んで いない者は 、忌明け後 用して運営さ れている。 出生届・丈 夫届が無く、 初御目見が それに当た 弘 前藩では、死 亡による跡目 相続、隠 居による家督 相続があった が、混 ③子 孫が無い時は 、身寄りより 養子を立 てる。 ②倅が 無く、二・三 男・孫の場合 は親族よ り申し出る。 小人一五人 を登らせる ほか、御手舟 栄通丸で 木材五〇〇石 を輸送してい り届けている 。町大工二 五人・屋根 屋五人・木挽 三人・鳶の 者三〇人・ 敷 からの要請に より、国元か らは緊急 のため、とり あえず金二千 両を送 意し ている。また 、召馬の飼料 も焼け、 入手の手配を している。江 戸屋 手伝っ ている。炊き 出しは、一人 白米二合 五勺として一 五〇〇人分を 用 怪我人の 手当てには、 医者のほか 蘭学研究の ため江戸に滞 在のものが ったようで ある。年齢 も一〇歳が原 則であっ た。今回の地 震においては 、 る。 男 子無之者身寄 之者名跡申 立候様、御 留守居組頭、 御広敷御用 候間、頭々 ニ而吟味之上、親族より跡式之儀早速申立候様、尤 死者有 之旨申来候、 依之右家内 之者為安堵 跡式御沙汰可 被仰付 ニ 一、 去 ル二 日之 夜 江戸 表大 地震 而 、所 々破 損之砌 詰合之 内、致 即 戸抱えの武家 奉公人も人宿 に引き取 らせず、藩の 手で行ってい ることが が 、非常時にあ たり藩の費用 を以て、 埋葬から追善 供養までを行 い、江 して 一人に一〇〇 疋を支給して いる。葬 式は通常親類 縁者の手によ った 明らか にした。定府 の三〇人は、 菩提寺へ 埋葬している ため、回向料 と 善供養がで きない勤番 の者のために 、永代祠堂 金を寄付し ていることを - 60 - に規則通 りに願い出る 。 緊急時 であり、多数 の家が対象に なるため 、緩和されて 適用されたも の 他 の場合と異な るかどうかを 考察する ものであった 。弘前藩邸は 埋葬場 ここ では、江戸の 町が地震で大 混乱をし ている中での 死者の扱いが 、 国 元においても 、同じように 取り扱わ れている。 所を探し、死 者八一人の内 、四七人 を、善行院の 承諾を得て 埋葬し、追 でな いかと考える 。 〕 「国日記」安 政二年一〇月 二〇日条 達、御台所頭、坊主頭、御召馬役 江可被仰付哉、沙汰之通被仰 わかった。 善行院と弘 前藩との関係 は、この時 だけであり 、緊急避難の 〔史料 付之、 5 前藩邸によ る埋葬依頼を 引き受けで きなかった ことが、両寺 の過去帳の 扱 いであったこ とがわかる 。長寿寺・ 碩運寺は、地 震の被害が 大きく弘 わかったが 、総数を明ら かにするま でには至ら なかった。 奉 行で三人、一 〇〇石取り の藩士二人 で一人の又者 を抱えてい ることが 可能に なった。この 先行研究の延 長線で江 戸藩邸をみる と、平時にあ っ 弘前藩は 、寛文元年か ら蝦夷地派 遣の軍団を 、貸人制度に より編成が 跡式に ついて、弘前 藩では末期願 を作成し 、目付が本人 の花押を確認 ても 貸人制度がな ければ役務を 遂行でき なくなってい ることが明ら かに 記載から 裏付けできる 。 する 必要があった 。しかし、地 震という 災害による死 者の場合は、 この ) 「江戸日記」安政二年一〇月三日条。 ( )善行院、日蓮宗、墨田区大平一丁目二四 帳を焼失し記録が残っていない。 ) 「江戸日記」安政二年一〇月二八日条。 ( )右同日記安政二年一二月八日条。 おわりに - 一。第二次世界大戦で過去 弘前藩 邸内の人は時 期によって違 いがある が、安政期に 定府は二二二 人、 その家族を一 家七人とみて 一五五四 人と推計、勤 番五一二人、 女中 藩との対応 に当たり、 処理の経費も 負担してい ることが考 察できた。 事故死の場合 、弘前藩邸が 関与せざ るをえず、幕 府・江戸町奉 行・他 は 藩主へ報告し 、指示を受け ることも あることがわ かった。 より 変化を生じ、 幕府奏者番に 伺って慎 重に取り扱い 、処分後も死 者名 病死に よる死体の弘 前藩邸内から の運び出 しは、藩主の 閉門・遠慮に 見届が必要 であること を明らかにし た。 診断により許 可になったが 徹底せず 、その際の末 期願は目付 による判元 病 下りは、文化 期に病を得て から一〇 〇日後に、組 頭の申立・医 者の 関係 とその働きを 明らかにする ことがで きた。 せざる をえなかった 。先行研究の 枠を超え て、弘前藩邸 の抱える雇頭 の 給が減少す ると、必然 的に江戸抱え の武家奉 公人を増員す ることで補充 人の存在が確 認できた。 国元から凶 作・蝦夷地派 遣により掃 除小人の供 上総小人は、弘前藩邸では寛保三年(一七四三)、一五〇人の上総小 藩邸 が関与して解 決する例も明 らかにな った。 転・薬 料等の経費は 、町方からの 借財に頼 らざるをえず 、未返済を弘 前 解消でき なかった。ま た、江戸の消 費生活の なかで、養子 縁組・長屋移 拝借金は、弘 前藩邸が二 度にわたる 救済策をとっ たが、藩士 の借財を な った。 )前掲書。 14 ( )右同日記安政二年一一月七日条。 ( 15 手 続きをとるこ とができず 、江戸・国 元において規 制を緩和し 、忌明け ) ( 後に願い出る 措置をとっ ていること が考察できた 。 註 ( )はじめにの註( ( 13 ) 「秘日記」 、弘前市立図書館蔵。はじめにの註( )前掲書。 ( 2 ) 「金木屋日記」弘前市立図書館蔵。 ( 3 五 八人を確認す ることがで きた。しか し、又者は、 家老で五人 、用人・ - 61 - 1 4 5 6 7 8 かったこ とが明らかに なった。 あり、年賦 による返納を ともなった 。上総小人 の二分は返納 の義務がな 片 付金の借用は 、御目見以 上が一両、 七歳未満の子 が御定めの 半減で 長寿寺・ 碩運寺が引き 取ってくれる ことが、 死後の安寧に 繋がっていた 同役によっ て埋葬されて いる。掃除 小人などの 武家奉公人に とっては、 対 する視線を確 認すること はできた。 勤番は、江戸 藩邸内の親 類縁者か し ていることが 明確になっ た。過去帳 の禅定門の戒 名が、約七 割を占め 察し た。特に、勤 番の埋葬を弘 前藩邸と 、長寿寺・碩 運寺の双方で 認識 を由緒書のな かに位置付 け、親類縁 者に認めさせ る行為でも あった。こ 最 大事に考え、 仏教の教え から先祖供 養を行ったが 、それは自 己の存在 近世 の幕藩体制下 にある武士は 、儒教に よる規範によ り、家の存続 を ものと みられる。 ていることか らも、両寺 が武家奉公 人の埋葬を引 き受けてい ることが裏 のことが 、江戸と国元 における追善 供養であ り、墓石の建 立であったと 正洞院 ・長寿寺・碩 運寺過去帳か ら、三ケ 寺と弘前藩邸 との関係を考 付けられ た。それでも 、安政江戸地 震の大混 乱の際は、長 寿寺・碩運寺 考える 。 か どうかを今後 の課題と考え ている。 (しのむら・ まさお 東 北女子大学 准教授) この ように弘前藩 江戸藩邸で考 察したこ とが、他藩で も行われてい た は大破 し、両寺への 埋葬はなかっ た。 江戸 安政地震の弘 前藩邸の死者 数を、通 説では幕府へ の報告から七 九 人 としているが 、先行研究が 八〇人と し、今回の考 察により八一 人と改 めることがで きた。定府 の三〇人は 菩提寺へ埋葬 しており、 勤番と菩提 寺へ葬送で きない者四 七人は、弘前 藩邸が関 与し、ようや く善行院への 埋葬が 可能になった 。災害時にあ たり、埋 葬・供養まで 弘前藩邸の経 費 で執 り行なわれて いることを明 らかにし た。 跡 式は非常の際 なので、江戸 ・国元に おいて、末期 願の花押を目 付が 確認する規定 を緩和し、忌 明け後に 取り計らうよ うに考慮さ れているこ とがわかっ た。 勤番の 者は寺請証文 により、同じ 宗旨の寺 院に埋葬され たのでないか とい う仮説を立て たが、確認で きたのは 三人だけであ った。病死一 人、 事 故死二人の場 合で、いずれ も江戸藩 邸の関与がみ られた。また 、菩提 寺とは違う宗 旨で扱ったも のが一例 あった。親類 縁者による追 善供養は 、 九人にすぎ ない。しか し、少数であ っても国元 から江戸に おける死者に - 62 -
© Copyright 2026