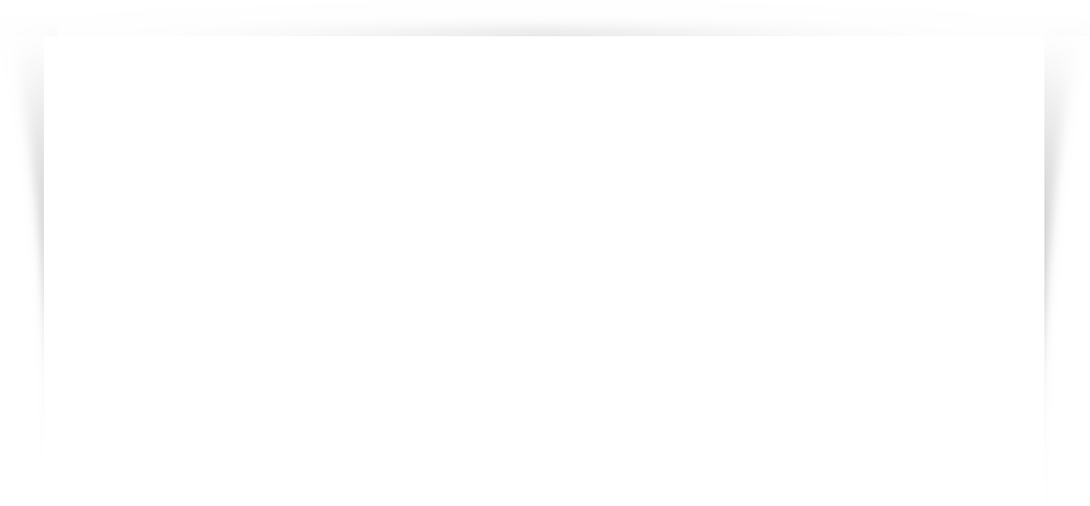
å¼ç¨ã¯å°å¦é¤¨æ°ç·¨å ¨é ãè¬èéã ã«ããã 西æ¬é¡å¯ºæ¬ã»ãä»è¦ç³» 諸æ¬
1欣一 、 一
1才
1妾β易ι止プく用{yι人﹂叉;也
・Ξ一
0)
いもに二:らく
・、三六)
B
A
門部王四詠物二首について
乞イ討イー三
ひbがLのいちの.つ,、、のこ大るまであ仕ずひさLみうぺこひにけり
あかしの・つらに上ι1ひのほにそいでぬる
t午1欣^ーヨー妾場立!L/くJ'︹エ︹メ、﹂1之也
(3
東市之殖木乃木足左右不相久美宇黛参永利
みわたせば
見渡 署 明 之 浦 尓 焼 火 乃 保 尓 曽 出 加 妹 尓 憇 久
(3
1
及
0
ノノ、
1﹄
,口
之
まとめたものであらう。切實な感動のないのは其の爲かも知
B1此の一首の1人1容は相開帥ち繁叢であるが、噸舗にょれぱ、
Ltさうしt:!丘なる自女長d)牙{イ{しを、﹁1一ぐに
の序の部分か作者の寶燃叢であることが知れる。・:(中略)
難波にあつて漁父の燭の光を見ての作であるといふから、そ
リノ\るままに1雄ノ\
のと系ことが出來る。そこには生活の衝迫があつたといふ
揣叢蒸に結びつけて表現するという技巧が、既に存在したも
よりも、災厶る技巧的結びつきで一首をなして居るのであ
へぱ此の作者の令工 0)の作も、さうした動機からの作と
は訂正を要するかも知れぬ。
に考ヘたのであるが、此の作を見るに及んで少しく其の考ヘ
見るべきかも知れぬ。彼の作に封してはそのことを寧ろ反對
る。、穫ば作歌む戲的技巧になつて居るのである。さうい
0
B歌第二句﹁明石
、
し
引用は小学館新編全染﹃萬葉集﹄にょる。西本願寺本ほか仙挙木
諸本にあってはA歌第五句二玉吾戀尓家利﹂、
まずは両歌に関する土屋文明璽崇私注﹄の評を参舌した
之浦爾﹂とするが、近時は非仙条に基づく校訂が支持される。
0
﹃私注﹄がしきりに懸念する、二首の下句に詠出された亦帯が表現
A1此の歌は一霧の作であるから、﹁う、、愈ひにけり﹂も植木を
、
織や小るのであらうと言ふ説もあるが、歌の趣はさうではな
者に実感的に抱かれているかどうか、については現時点ではもはや
の下緑誓なる対象物を明示しながら、あくまでその対象物を契
問題にする必要がないけれども、二首の題詞がともに﹁詠﹂﹁見﹂
上の句は第四句の修飾である。尤もⅧ蒔すでに一霧なる
し
作風が行はれて、此の歌もその一體として作られたものかも
釘れないか、作者はそれに戀愛の意峠を村たせかけて一首を
1
、
0)も眼前の景物に接
こ
機の位置にとどめて歌文を恋情に収束させる顕著な共通性には蓉一
同じ門部王の東市の木を見ての作会工
しなければなるまい。器 久 孝 ﹃ 一 染 集 郭 ﹄
して思ひを述ベた黙は同じであり、何か相通ずるものがあり、
共に同人の作と見るべきかとも患はれる。
な誹ルと歌の主情との間に生じるある種の棚楯・不訓和は、
と言及するのもその点をとらえてのことである。もちろんこのよう
同坂上郎女初月歌一首
(6
・九九三)
打立ちてただ三U月の眉根掻き日長く恋ひし君昼ヘるかも
大伴{壽石竹花 歌 一 首
(8
・一四九六)
我がやどのなでしこの花盛りなり手折りて、一目見せむ児もがも
宴廊霪ヨ河梅花 歌 一 首
(18
・四一.Ξ四)
雪の上に照れる河夜に栴の花折りて送らむ愛しき児もがも
右一首十二月 大 伴 宿 祢 家 持 作
見漁夫火光歌一首
・
B歌に突出し
]9 ・四
鮪突くと海人の燈せるいざり火のほにか出ださむ我が下思を
A
ノ\
いることの土健は小さくない。表現史的観点に立つときには、{永持
(注])
ない恋情が、おそらく按近した時期に同一作者にょって詠出されて
活の衝迫﹂不在の作と一言わしめた、いうならぱ具体的刈象に収束し
た個性とは見なしがたいか、﹃私注﹄をして﹁切牙感動のない﹂﹁生
など・一奪とその周辺に広く見出されるのであり、
ノーー'、
周辺に試みられるこうした一隨の先朧に門部王作歌が位置するとい
以下に若干の検討を加える所以である。
、フ希を与えることも可能だ。
二
A歌下句鳶の話題に収斂することにつき、西宮一民氏﹃萬一釜
市は人の集まる処で、歌垣も催され、異性昼う機会が多かっ
<恐巻第一ミは、
B歌の恋曾質について岸本田需璽峯攷證﹄の﹁故
たから、それにふさわしい相聞歌的内{谷に構成したものである。
と竺、
郷の妹系岩思ひの穂にあらはれぬと也﹂とする解を偲俗氏﹃萬
上三句では旅先の物に、下二句では故郷の妻に気を使っている
一黍釋竺﹄に、
わけで、一首の中に旅の歌の作法を封じ込めたもの。
と敷衍するが、いずれにも従うことができない。東の市の殖木から
が示唆するのは、類似する表現の、
腎一にまで連想を延ぱすのは距航が遠すぎるし、﹁ほにそ出でぬる﹂
(9
・一七六八)
石上布留の早稲田の穂には出でず、心の中無ふるこのころ
・一三七五
一1出でて言ははゆゆしみ朝顔の穂には咲き出ぬ恋もするかも
(W
(W
・一三八五)
秋萩の花野のすすき穂には出でず我が恋ひ渡る隠り妻かも
はだすすき穂には咲き出ぬ恋を我がする玉かぎるただ一目のみ
2
(W
・一ご三一)
樹木の託、が期待させる一般的稱想はおおよそ右倫囲であり、
A
るにせよ樹木の成長・繁戊を称賛していようからこの忰内に収まる
歌上句は第三句の意を﹁木1垂ル﹂﹁木1足ル﹂のいずれに受け取
見し人古女に
などから看取されるように、自身の胸の奥深くに潜ませる秘めた恋
右と同じ検証をB歌にも施しておこう。題詞﹁見爽X燭光﹂がB
が、下句は明らかにそこから逸脱している。
,、よ3
であって露林琶家郷に残した妻ヘの墨嵳は捉質である。
とはいぇ、山田孝雄一萸来染難露が﹁題詞にわざと﹁詠﹂とか
展開のありようもA歌に等しいことを再度鵄岫したうえで、風父
歌上三句に過不足なく隆込まれている点は明駆あり、下句ヘの
きたれぱ、これは如何にしても相開のうたにはあるべからず﹂の認
ひてうたへるものなり﹂と主張したところが当たらないのは前引
・-
0四二市原王)
・四一五九大伴{壽)
・三九四)
・二五六柿本人麻呂)
・-
00三葛井大成)
七讐の海人の釣し燈せるいざり火のほのかに妹を見むよしもが
(松・一三六九)
能登の海に釣する海人のいざり火の光にいませ打待ちがてり
もつとも、繰﹂十二椅旅発思中の、
﹁妹﹂ヘの恋を導くのは少なからず飛躍がある七言わねぱなるまい。
などをその範時に含むと認められるのであり、こうした文脈から
(リ・三八九九作者未詳)
海人娘子いざり焚く火のおぽほしく都努の松原思ほゆるかも
(6
海人娘子玉求むらし沖つ波恐き海に舟出せり見ゆ
(3
飼飯の河の庭良くあらし刈り燕の乱れて出づ見ゆ海人の釣舟
のような旅惰・旅梦τ主誓した内容がまず墾疋され、さらに、
(巧・三六二二俳糧人作名米詐)
山のはに刀傾けぱい、ざりする海人の燈火沖になづさふ
(7
紀伊の国の雑賀の浦に出で見れば海人の燈火波の間ゆ見ゆ
燭光﹂の露﹄に符合する内容を染中に求めれぱ、
識のもとに﹁これも市之樹ミ惣ひつつぁりしが、今見れば云々とい
﹃私注﹄の言うとおりである。他に例を見ない条﹁東の市の殖木﹂
がA歌にうたわれる点を注視するなら、それが予め用意された歌題
︹住2︺
であった可能性がきわめて大きく、﹁詠1作歌﹂七詠物ヘの志向を
儿帳面に記した霄式は、その逆の判断1諫歌内{谷にあわせて題詞
呈録であるか否かは留保するとしても、作歌時点の環境を正確に
を後補したという把握1を許容しない。当該腰詞は、門剖王自身
の殖木﹂を、靴のとおりに隆込んでその﹁木足る﹂さまを嶺美的
伝えていると判断できる。門部王はその題を踏まえて拙恕し、﹁市
の文脈内に{莅したのである。
に描くと同時に、それとは大きくレベルの述、つ亦俗をあえて荘机き
(6 ・九九0 紀鹿人)
茂岡に神さび立ちて栄えたる千代松の木の年の知らなく
(6
一つ松幾代か経ぬる吹く風の声の清きは年深みかも
(巧・二六一三俳糧人)
我か命を長門の島の小松原幾代を経てか神さび渡る
(19
磯の上のつままを見れば根を延ヘて鋭休からし神さびにけり
3
も
あるいは 寄 物 陳 思 に 分 類 さ れ る 、
(W
・一三七0)
ることは疑えない。この作者の風流侍従としての吹叢をここに思い
(Ⅱ・二七四四)
良・沈病自哀文のN例を見るものの瓦X﹂は当該例のみ、﹁燭
の語は八五三歌序、三九六一歌左注、四三八題(前掲)および憶
再X燭火﹂については若干の考慮を要する。萬一泰中に﹁漁夫﹂
合わせておくことも不当ではあるまい。
を祝野に収めるときには、﹁海人のいざり火﹂﹁燈火﹂と異性ヘの恋
すずき取る海人の燈火よそにだに見ぬ人故に恋ふるこのころ
慕とがさほど隔絶してはいないことが了解できるものの、右諾例は
ともに漢語として珍しくはないが、再X﹂からは誰もがまず
0
﹃郭﹄が和名抄﹁釜辞云、渙釜桟而去、墾一云漁翁︹無良岐き
昔岼や史記また文選に収められる屈原の故事を想起するはずだ。
1J
火﹂も二七四四歌文に用いられるだけで題詞中の使用例はほかにな
あって、 B歌と連続した発想基盤に立つとは言いながら発想の方向
恋情を表出するための序としてそれぞれの景が選択されているので
を逆にとる点を見届ける必要がある。当該B歌と同様に変山倫を
引き込む詠物歌としては前引した家持四二八﹁見漁夫火光歌﹂が
に等しい﹂と注するのには丕条ある。この語にアマの訓を与える
を引きながら﹁単に浄夫、浄人の愆にも用ゐられ、今も海人といふ
而問之日、子非三閻大夫與。何故器斯。(玉巻三十弓
屈呼既放游咲江沖行吟澤畔。師色蹴埣、形谷枯稲。池父見
きてネはない。
のはよいとしても、西X﹂の文字列が採用される点を看過するべ
わずかな例外である。
三
A・B両歌の構想の共通性を右のように硫かめれば、それぞれの
ある。もとよりこれがA歌題詞の直接の典拠であるとは断じられな
屈原が放逐されて江曹遊び渙父と避遁する、よく知られた一節で
いけれども、この一Wにおいて辺境の水辺に舞台が求められる点
むしろ不自然だ。いずれも四字句ヘの規格化を経ており、前名は平
城京に属する近景を、後者は旅先・州波に属する述景を誘心とする
と、
題詞﹁東市之樹﹂匝X燭火﹂の際やかな対照を偶然と扱うことは
点において対比的である。両歌四松時期は、配列上おおよそ親ボ
か呈絡があると予測することは許されるだろう。
す。ただ遠方に見ゆる漁火をおしあてに明石の浦のと定めたるに
井上通泰武泰新考﹄は﹁明石の漁火浪華まで見ゆべくもあら
B歌に﹁明石の浦にともす火﹂が描出される点との問に何ほど
第三期を示す位置に置かれていること以外に限定できないが、三一
なっている様態を勘案するかぎり、大きな時冏差が横たわるとは考
七歌から三二五歌までが山部赤人上将虫麻呂関係歌の一括掲載と
て﹂と述ベて、
(3
・ニハ三高市黒人)
住吉の得名津に立ちて見渡せぱ武庫の泊まりゆ出づる舟人
えにくく、陌翁・歌内容を含めてあたかも同一工房の鋳型に出るか
あろう。小ノなくともA・B歌が等しい詠歌環境のもとに生成してい
と思わせる二首は直接的な関係に結ばれていると見るのが穏やかで
4
一佳れたということだ。饗呆としての海人であれば難波の海に多数
の着想を与え、それに適介する門京として﹁明石の浦にともす火﹂が
これは言うまでもなく見えない。が歌として、難波から見はる
こそが似つかわしい
舟を浮かべていようが、午老いた浜Kの燭火は都を述く剛れた海辺
に同じいとし、西宮氏﹃全辻は、
かす漁火を、歌枕的な音誕にょって﹁明石の浦﹂の漁火と表現
染中に多用される﹁見渡せぱ﹂の表現は、、赤の視界に入る対象物
(2。・四三九七)
同征せぱ向つ嫌の上の花にほひ照りて立てるは愛しき誰が妻
(W ・一八七二)
見渡せぱ春日の野辺に波立ち咲きにほへるは怯花力も
(7 ・一一六0)
雛波潟潮于に立ちて見渡せぱ淡路の局に鶴渡る見ゆ
0
し、それほど﹁明し﹂(明暸だ)とい、つ意昧を祭せているの
かったのである。
である。明石は見えなくても、明石の渙火でなくてはならな
三肌を深化させるが、難波周辺の漁り火をあえて祝界から外し
﹁明石の浦﹂を点描する発想の述和感が右の説明にょってすべて觧
消するとは思えない。なるほど明石が畿内外の境界として都びとの
1現・笑に見えるか見えないかは別にしてーをとらえ、その対象
告罷中に固定されていたことは認められるものの、明1iと﹁漁火、
がたく、集中にその両者を結びつけるものは、
・二五四)
あり、初句にこれを据える一首はそうした趣旨を強く娚待させる。
︹江1︺
物か主体にある種の感懐を抱かせるという文構造を通例とするので
との取り合わせ系枕と認定しうるほどに{馨しているとは見なし
(3
燈火の明石大門に入らむ日や漕ぎ別れなむ家のあたり見ず
0
い刈象物を提示する点でまず通例に背き、さらに下句に予想外の恋
ところがB歌は﹁在挑波﹂の条件下では容易に視界に入りそうもな
﹁在難波見洪X燭光﹂四詠題に正しく軟忠旦9るように見せながら不
仙を展開させるため、二重に期待を喪切る次第となる。結果として
見える見えないの論議に加わるよりも、いまは﹁在難波﹂の惰保
の一例し か な い
与の題を的確に受け止めたうえでいかに巧みな椛想を提示するか、
・
Bの僅か二首を観察しただけだが、こうした・愆外性ある展開
を提供する点に門部王四霧歌の特質があると豹乢定してょいのでは
A
研和をも抱え込む油帝rな作が将来された。
自体が設定された条件であると把握するほうが醗醜的であろう。所
の機知が詠物において試される課題であるとするなら、そもそもB
図をけ度すれぱ、摂津・難波を起点にして同国内のもつとも述い地
ないか。再三会屈した四一、ニハ歌につき一注釈.一が﹁門部王の作に
歌か{青ぞうたっているという前提に立つ必要かない。円部王の意
点を﹁見述すとうたい、聴き手統者)の打美を突くねらいがあっ
よつたものであらう﹂とした判断は正当で、門楽の知性の踏襲を
奪が志向するのは理由のあることである。
たのではないか。そしてその予想外な発想を誘発する要因だ僻叩
再K﹂の語性に内在するのだと小稿は老えたい。屈原の故那に迫
結するのでなくとも西X燭火﹂が門卸王に辺境のうらぶれた"小
5
四
力大も01
おもひやゆかし
みちの右がてを
巻四所収﹁門部王恋歌﹂ヘの見通しを立てて稿を閉じる。
しほひのかたの
門部王恋歌一首
あうのうみの
・五三六)
飫宇能海之塩干乃南之片念尓思哉将去道之永手呼
(4
右門部王任出雲守時妥部内娘子也未有幾時既絶徃
来累月之後更起愛心仍作此歌贈致娘子
き、門部王のかかる詠風が和歌説話の形成を促したという推測も成
ついては別稿に指摘したことがあるが、それとの関連においても門
︹注6︺
り立つかもしれない。風流侍従と巻十六所載和歌説話との親縁性に
同時代に二人の門部王が存在することは周知だが、小稿では
部王作歌にはさらに注目する必要を感じる。
1
右を俎上に荘た新谷秀夫氏は二首が﹁恋を主題とする歌﹂であっ
一歌題詞脚および一.0一三歌左注下尋き入れをひとまず是
その考証に取り組むことをせず、
見解である。小稿の趣旨に即して言い換えるなら、一首はそもそも
い﹂と述ベる。﹁伝訥﹂の認識を除けぱ大筋において首肯してょい
訥されながら亨堂されていたものがのちに記載されたと見て大過な
で﹁当啄歌の左注は、娘子をめぐる門部王の恋として歌語り的に伝
に澤袴久孝﹁万葉作者襍き(﹃万冴作品と時代﹄岩準居、
従﹂の一人とされる人物に相当すると考えておく。関連論考
に捌内王の子、長親王の孫と位置づける、家伝下に﹁器侍
﹁授従四位下大原真人門部従四位上﹂と見え本朝皇胤紹運録
真人姓を賜った高安王の弟であり同書天平十四年四月戊戌条
認する。すなわち、続日本紀天平十一年夏四河甲子条に大原
A・B歌題詞脚のほか三七
て﹁左注で語られるような事実は存在しなかった﹂と判断したうえ
具体的対象を持たない、器おない恋を詠じたものであって、左注
記す﹁任出雲守時﹂をも存疑とし、﹁いまひとつの歌(火二一・三七一)
昭和玲年)、黛弘道氏﹁万柴歌人﹁門部王﹂小考﹂(家衆上
物の艘にして、い、づれもある外物をとりて、それを客觀とし
げて詳細に検討し、﹁詠﹂を題にもつものが﹁支那に所却線
この書式に関しては山田﹃講義﹄が﹁詠﹂の集中全用例を挙
代文学﹄第八集、簡書院、昭和訟年)がある。
釡3︺
がそれに実態を付与したということだ。もつとも、新谷論は左注に
2
題詞・左注に高度の加工を施した作品か鳥π時点に遡源する手段
しておかしくない﹂と述ベて現実の詠作事情に踏み込もうとするが、
謀んだ出器地名をふまえて、都などで詠んだ歌であってもけっ
はない。左注に展開する逸栗実在の門部王の謬とは等号希ば
では岩波新大系武美﹄に﹁陌葡の﹁詠みて作﹂るという
てうたへるもの﹂であることを論定している。近時の校輩、国
﹃萬葉代匠記﹄が﹁木垂ナリ﹂を主張し、﹃萬葉考槻一璽﹄に
形式は珍しい﹂の言及がある。
つことを確認しておけば足りる。
3
れず、歌の表現内容から抽出される印象のほうに岫筆な一致点を持
五三六歌が本来{益のない恋をうたったものであるなら、小稿に
検討を加えたA・B歌との質の近よりをたやすく見出すことがで
6
4
の理解は対立して現在に至るが、﹃時代別鼎叩大辞典上代編﹄
﹁木の年ふりて、禁ホの足れるをいふ﹂として以来、この語
に﹁﹁木足﹂を正字とみて、樹木の枝葉の充足している意に
解すべきである﹂とするのが的を射ていよう。いずれにせよ
平城京東市か設枇後一定の年数を経ての情条L揣写Lた表現
と見られ、的四一冴取り込みが、腎られる点に注愆してお
0
一九一三歌のように恋歌の序に用いられて当験と近い
きナし
新谷秀夫氏﹁門部王の﹁恋の歌﹂を読む﹂兪岡市万葉歴央
文構造の例も見られる。
5
川薪尚之'肌の.需と乃一女1市原王を中心に1﹂(一万菜
館紀要﹄第巧号、平成口年3月)
6
(かげやま・ひさゆき本学教授)
集の今を者える﹄新典社、平成幻年)
7
© Copyright 2026

